廊下の隅々まで下の句が散らばる廊下。その中央にでんと居座る弟。彼は眞代から目を離すと再び手元の上の句を読み始めた。
「あきのたの」
「ストップ」
眞代は後ろ手で襖を絞め、弟の声を遮った。
「さっき言ったでしょ。今ここに友達が来てるの。遊んでる最中なの」
「ふん」
弟は眞代と目を合わせようとせず、上の句の山札をシャッフルし始めた。
「ミズハ!」
眞代は語気を強めた。
「私の友達が困るの。だからここで百人一首するのはやめて。あと三十分したら好きにしていいから」
「ここは僕の家だよ。友達とやらの家じゃない。どこで何しようが僕の勝手だろ」
「もう!」
眞代は一歩踏み出した。下の句を片っ端から拾い集め、両手でひとまとめにして居間へと移動する。
「急に何するんだよ」
文句を言いながら弟が後について入って来た。眞代は襖を閉める。
「ここでやって。友達に迷惑掛からないから」
「はいはい、よーするに友達に怒られるのが嫌ってことね」
「何言ってるの! 二人に楽しく過ごしてほしいの。折角うちに来てくれたんだから」
言いながら、眞代は居間の床に下の句の札を並べ始めた。弟は突っ立ったままじっとその様子を見ていたが、座布団の上にどっかりと腰かけて眞代に話しかけてきた。
「うちに来てくれた、ねえ。ホントに久しぶりだよねあの二人」
「え? あ、うん」
弟からの雑談が珍しく、眞代は少しの間手を止めた。
「だいぶ前はよくうちに来てたよね。それがここ2、3年全く顔を出さなかったね」
「まあ、ね」
弟の言う通り、しばらく萌々と翠の二人は眞代の家に来ていない。来たがらないのだ。
誘っても「萌々か翠の家でいい」と言われるようになり、眞代もそのうち呼ぶのを諦めてしまった。
「うちの噂のせい? あーそれともアレ? はやりのテレビゲームに夢中なの、友達?」
「うん・・・」
「あーなるほど、この家にはゲームなんてないからな。それなら行かなくていいってなるね」
親の方針で、ゲーム類は一切家に置かれていない。つまりテレビゲームはできないわけで、二人もうちに来ないのだ。
「てかずっとゲームしてんだ、姉さん。付き合わされて可哀そうに」
「何言ってるの。皆で遊ぶのは楽しいよ」
「そう? ゲームばっかでよく飽きないね。てかそもそも姉さん、ゲームはあんまり好きじゃないでしょ」
弟が頬杖をつき、上目遣いで見上げてくる。眞代はとっさに返答できず目を逸らした。
「好きでもない遊びにずーっと付き合わされてさ、それって本当に友達って言えるの?」
「友達だよ」
それには間髪入れずに答える。
「一緒にいるだけでとっても楽しいんだもん」
「ふーん」
「とにかくね、久しぶりに家に来てくれた友達に、居心地悪い思いはさせたくないの」
「そんなに大事なんだ?」
馬鹿にするように首を傾げる弟。
「そりゃそうでしょ」
「なんでもいいけど、僕には理解できないな。『召使い』なんかが大事なんてさ」
「ちょっとミズハ! その話は・・・!」
眞代が声を荒げた瞬間。背後の襖がバン、と音を立てて開けられた。弟がしまったというように座布団から立ち上がる。しかし遅かった。
萌々が居間に入って来たかと思うと、弟に向かって大きく手を振り上げたのだ。すんでのところで眞代はその手を掴んで止める。
「萌々ごめん、でも暴力は・・・」
「ねえ」
萌々はこれまで見せたことのない険しい表情で眞代を睨んできた。
「その子に言ってたわけ?! モモの昔の話!!」
「ううん、そんなこと!」
「じゃあなんで知ってんのその子が!!」
掴まれた手を振りほどき、弟を指さす萌々。
「あの時言ったよね!! 誰にも言わないでって!! うんって言ってたじゃない、嘘つき!!」
大声で叫んだかと思うと、萌々は急に黙った。肩で息をしながら、その目が下へ下へと向いていく。
「嫌なこと思い出しちゃった。ミドリンにも知られちゃったし・・・あー最悪」
誰に言うでもなく呟いた萌々は、そのままくるりと踵を返した。
「もういい、モモも帰る」
「ごめん、萌々!」
眞代は追い縋った。
「せっかく来てくれたのに、こんなことになっちゃって」
「何他人事みたいに言ってんの!! あんたのせいでこうなったんでしょ!!」
靴を履きながら、萌々は敵意を込めて眞代を睨みつけてきた。
「ホント、友達になんかならなきゃよかった」
それだけ言うと、萌々は眞代に背を向けた。ガラス戸が、割れるのではないかと心配するほどの大音を立てて閉められた。
眞代はしばし呆然としていたが、はっと我に返り客間へと向かう。
「翠、萌々が帰っちゃって・・・」
そこに翠の姿はなかった。玄関に戻ると靴も消えている。萌々より先に帰ったらしい。
友達二人が突如としていなくなり、眞代はまたもや呆然とした。
(私が中々戻らないから居間の外で聞き耳立ててたのかな・・・)
そんな、今更意味もないことを考えずにはいられない。先程のことが受け入れられずにいるからだ。あんな暴言を吐かれたことなど今までなかった。今日は葵がいなくても、三人で楽しく遊ぶはずだったのに。
だがそこまで考えて眞代はぶんぶんと首を振った。今はそんなことどうでもいい。萌々が傷ついたことが問題だ。
「ミズハ!」
眞代は部屋に戻ろうとしていた弟を呼び止めた。
「さっきの、良くないよ」
「何がだよ」
弟は鬱陶し気な顔で眞代を見た。
「僕は別に本人に聞かせたわけじゃない。あの人が勝手に聞き耳立ててああなっただけさ」
「でも家に来てたのに、あんな話をしちゃだめだよ。だからさ、明日一緒に萌々に謝ろう」
「やなこった」
「ミズハ!」
「ちょっと、帰ったと思ったら何の騒ぎ?」
襖が開き、母が顔を出した。
「お母さん、その、実は」
どう説明しようかと思っていると脇から弟が口を挟んだ。
「姉さんの友達に叩かれそうになりました」
「なんですって、眞代、どういうことです」
母は眞代に鋭い目を向けてきた。
ーー
それから三十分後。浜崎家の居間で、家族会議が開かれていた。上座に両親、下座に眞代と弟が正座している。今は、弟が両親に向かって詳しい経緯を説明しているところだ。
「僕は友人の家に呼ばれましたけど、勉強があるのでさっさと帰ってきました。予習と、それから漢字の書き取りがまだだったのでそれをやってました」
弟は眞代相手とは打って変わって、背筋をしゃんと伸ばし丁寧すぎる口調でハキハキと話している。小柄だが吊り目がちの母と、痩せて背が高く筋肉質の父がそれに耳を傾けていた。
「書き取りのお陰で、今日の漢字テストも満点でした」
眞代の方をちらちら見ながら弟は付け加えた。
「そうか、当然だな。そういえば眞代」
父は黙っている眞代に目を向けた。
「今日は確か、先週の理科のレポートの返却日だったな。無論、最高評価だったんだろうな」
「A-だった。要点が一個抜けてたみたいで」
でも、その前がB+だったので上がっている。頑張った。
だが父母は気遣わし気に顔を見合わせた。
「やはり、良くない影響を受けているんだな」
「そうね。まあいいわ。瑞波、続けなさい」
「はい。やることが全部終わったから、百人一首をしようと思いました。ほんとは客間でやりたかったけど、姉さんと友達に占領されちゃったので仕方なく廊下でやりました。そしたら姉さんに、居間に連れてかれて。で、二人で姉さんの友達のことを話してたら、ウメノさんが突然僕を叩こうとしてきたんです。結局叩かれませんでしたけど」
「暴力とは嘆かわしい。それも自分より年下の子に」
「やっぱりろくな教育をしていないんだな。あんなもので遊ばせている時点でどうかとは思っていたが」
「ちょっと待って」
聞いていられず、眞代は口を挟んだ。
「ミズハは大事なことを言ってない! ミズハは、萌々が言われたくないことを言ったの。だから萌々は怒ったの」
「なんて言ったんだ」
「それは」
言えなかった。萌々を傷つける言葉を自分の口から出したくなかった。
「まあいい、どうあれ、瑞波への暴力は許せん」
「電話します。謝ってもらわないと」
母が腰を浮かせる。眞代も慌てて座布団に膝を立てた。
「待ってお母さん!」
「眞代、座りなさい」
静かな、しかし有無を言わせない口調。眞代は母を目で追いながらも再び正座に戻った。
「何故お前はその子を庇うんだ。弟が叩かれそうになったんだぞ」
「で、でも、萌々だってものすごく嫌な気持ちになったはずだよ。私、分かるの。友達だもん!」
「前から思っていたんだが」
父親はぐっと腕を組んだ。
「お前はもう少し、友達をちゃんと選ぶべきだった。私はどうも好かん」
「え・・・なんで」
「ゲームなんてものを、うちの子に教えたからだ。あんなものは、子供をダメにする。つまらん色付きの欠片を手に入れることに夢中になって、大声で喚いたり見境なく暴言を吐いたりする。姿勢も視力も落ちる。効果音だとか光る画面だとか、そんな中身のないものに限って中毒性があるから時間を浪費する。それでゲーム以外の全てがおざなりになるんだ。普段の生活から勉強から何もかもがな」
「・・・」
眞代は黙って父親の話を聞いていた。いつの間にか視線は下がり、俯いてしまっていた。
言い過ぎだとは思う。だが、父の主張自体は間違っていないんじゃないかと感じたからだ。
(時間をいっぱい使う、他のことが何もできなくなる・・・)
特にそれは、眞代が常々考えないようにしていたことだった。ゲーム一つで時間はあっという間に過ぎてしまう。後で動画を見たり、ノートにまとめたりもしないといけない。大のゲーム好き二人に合わせるために、眞代は結構な時間を使っている。
「そして出来上がるのが、刺激と格付けを追い求めるだけの大人だ。お前の友達は、お前をそんな風にしてしまいかねん」
「二人はそんなつもりないよ! 私だって別に」
「黙って聞きなさい。お前の友達は、お前に悪影響を与えている」
「そう、ほんとうにそう。あなたたちにあんな風になってほしくはないわ」
廊下から母が戻ってきて再び座布団に腰を下ろした。今の間に電話が済んだのだろうか。眞代は居ても立っても居られず母に尋ねた。
「お母さん、萌々はなんて?!」
「何も言わなかったわ。用件を伝えたら、無言で電話を切られたの。本当になっていない子ね」
母はため息をついた。
「あなたの交友関係に口を挟みたくなかったんだけどね、あの子達と友達になったのは間違いだったんじゃないかしら」
「そのようだな。とにかく眞代、明日お前からも言いなさい。瑞波にちゃんと謝るように」
「そんなの、そんなの言えないよ!」
眞代はぶんぶん首を振って立ち上がった。
「そりゃ、暴力は良くないけどミズハだって悪かったんだよ! それに、なんで、なんでお父さんとお母さんは・・・」
その先の言葉は喉の奥につっかえて出てこなかった。眞代は口をきゅっと結び、逃げるように自室に引っ込んだ。
冷たい敷布団の上に寝そべり薄い毛布で首から下を覆う。だがそれだけではなんだか心細くて、横向きになって膝を抱え込んだ。
(なんで、私の友達のことをそんなに悪く言うの・・・)
さっきはそう言いたかったのだ。でも言えなかった。
悪く言う。自分の家族が、大事な友達を。それはとても辛いことなのに、改めて自分の口から言うなんて耐えられなかった。
「萌々もこんな気持ちだったんだよね」
萌々がいわゆる「パシリ」として、クラスメイトにこっそりと使われていたのは小学四年生の頃だった。それに気づいた眞代に萌々は口止めしたのだ。「このことは誰にも言わないで」と。
萌々はちゃんと「パシリ」をやめたものの、なんで先生と親に言ってはいけないのかと眞代は納得できなかった。が、その後徐々に萌々の気持ちが理解できた。萌々は傷ついていて、そのことを蒸し返されたくなかった。もう考えたくなかった。忘れたかったのだ。
なのに今日また、思い出させてしまった。
「やっぱりダメだよね、ちゃんとこっちから謝らないと」
明日、自分一人でも萌々に謝ろう。それで萌々の心が和らいだら、萌々と弟が顔を合わせることだってできるはずだ。
「大丈夫、きっと大丈夫」
眞代は膝をぎゅっと抱え込んだまま眠りに落ちた。
ーー
だが翌日ー問題の木曜日の五日後ー。
「萌々、おはよう」
「・・・」
眞代が挨拶しても萌々は無視して何も返さない。机の上に頬杖をつき、むっつりと黙り込んだまま眞代の方に目もくれない。
「あっ、萌々ちゃんおはー」
「おはよっ、今日ツインテなんだぁ。かわいー」
別のクラスメイトとはにっこにこの笑顔で話している。眞代はぐっと唾を飲み込み、自分の席に着いた。
(今日は無理かもしれない。でも明日ならー)
と、不意に視線を感じた。教室の前の方からだ。
「あっ」
今登校したばかりの翠が眞代を見つめていた。無表情だがそれはいつものことだ。眞代は少し安心して腰を浮かせかけた。
「翠、おはよう」
翠は応えることなく眞代の前をスルーして席に着いた。萌々とも挨拶することなく机に座って時折眞代を見てくる。
(翠、萌々のことで気まずいのかな)
「おっは、眞代ちゃん」
「ちょっと見てよー」
「あ、うん」
気がかりだったが、クラスメイトに呼ばれたので席を立つ。
戻った時、机の中にメモが置かれていることに気づいた。
『ゲーム好きって言ってたのに嘘つき。イヤイヤやってるんなら、もう一緒に遊ばなくていいから』
反射的に翠を見た。彼女は目を逸らすことなく眞代と、その手の中のメモを凝視している。
(翠・・・)
突然のことで頭が追い付かなかった。チャイムが鳴るまで、その場に凍りついたように動けなかった。
その日一日中、眞代は上の空だった。先生に当てられても気づけなかったし、廊下でよくつまずいては友達に心配された。
(萌々と翠を傷つけちゃった。嫌われちゃった)
弟の振った話題に乗ったのが間違いだった。本人のいないところでの噂話なんて普段は絶対しないのに。それで、萌々には嫌なことを思い出させた。翠には不愉快な思いをさせた。
幼稚園の頃からの大事な友達にこんな思いをさせるなんて。こんなことになるなんて。
(どうしようどうしよう、どうしたらいいの)
ずっとそのことばかり考えて胸が苦しかった。家に帰っても、鉛筆を握る手が震えて勉強にならなかった。
眞代は机から離れて冷たい布団に倒れこんだ。
『友達になんかならなきゃよかった』
『もう一緒に遊ばなくていいから』
目を閉じても、それらの言葉が頭に突き刺さってくる。眠ることができず、何度も寝返りを打った。
次に目を開けた時、外はまだ明るかった。だが小鳥がチュンチュン鳴く声でいつの間にか朝になっていたのだと悟る。
「急いでお風呂入って、学校、行かなきゃ・・・」
だが体が重かった。とても起き上がれそうにない。眞代は学校を休んだ。
そして次の日も。その次の日も。冷たい布団の上から起き上がれなくて。
眞代は学校に行くことができなくなった。
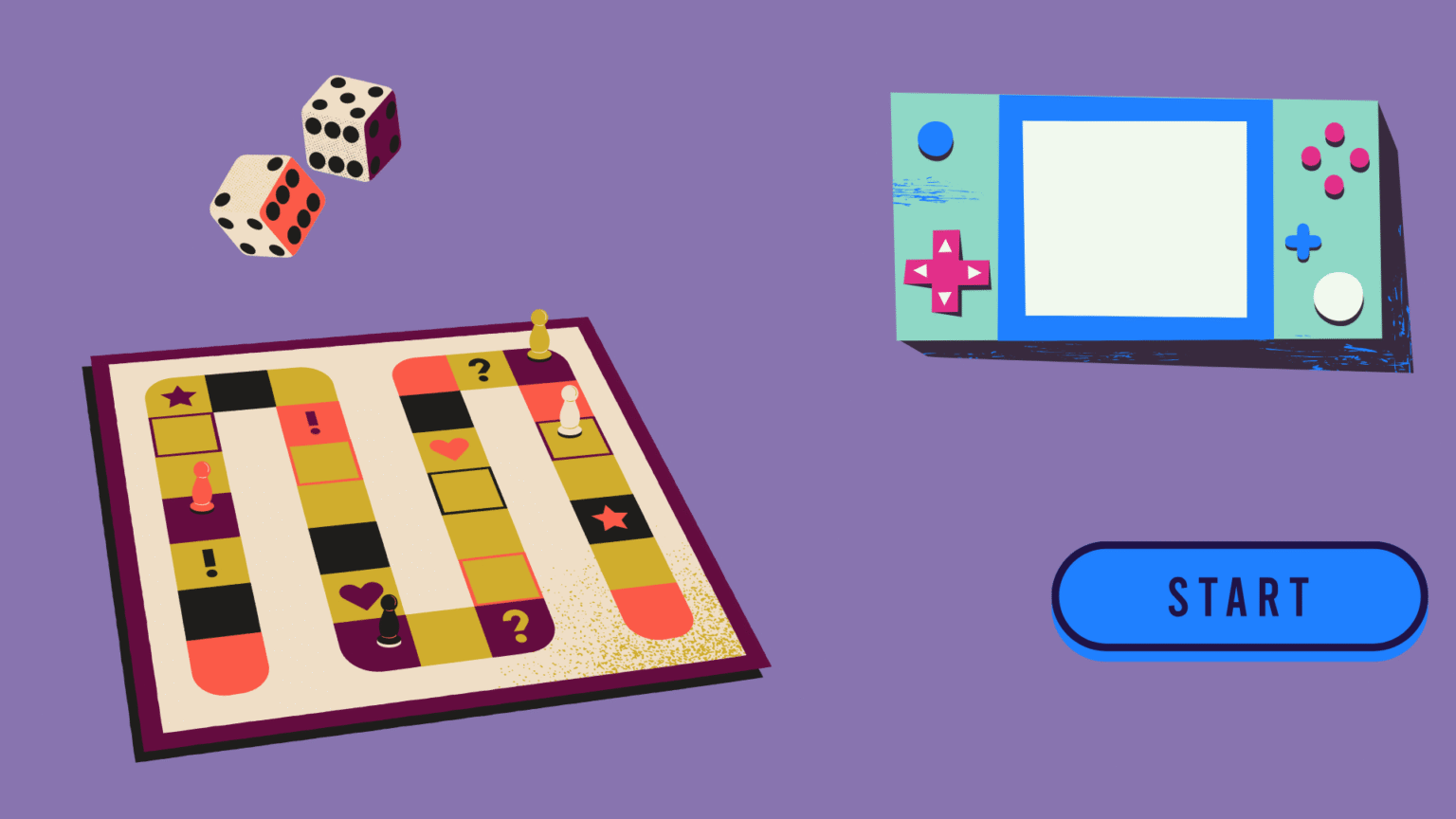
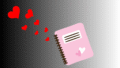
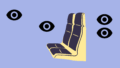
コメント