「ボードゲーム、カフェ」
葵は再度、口の中で繰り返した。ボードゲームは好きだ。カフェにも行ったことがある。だけどその二つの言葉が組み合わさるとなんだか不思議な感じがする。
「えっと、ボードゲームを売ってるカフェ?」
「おしい! ボードゲームで遊べるカフェだよ」
「ふーん・・・そんなのあるんだ」
「パパの友達がね、最近駅前にオープンしたのさ。少し遠いけど徒歩で行ける距離だしちょっと行ってみないか?」
「えー・・・ボードゲームなら別に家でやればよくない?」
わざわざ外に出てやりたいとは思わない。知らない人がいっぱいいる外に。
「小さい店だけどね、ゲームの数はものすごいんだってさ。そう、ざっとうちの五倍か六倍か・・・」
それを聞いて葵は躊躇った。ボードゲームのせいで友達を失ってから、父とも遊ぶ頻度はめっきり減った。前ほどには、ボードゲームをやりたいと思えない。
だが六倍、六倍ということは・・・。
「行ってみてもいい、かな」
自分の知らないゲームがあると思うと、やはり心が動いてしまう。
ーー
駅前の通りに面して並ぶブティックや百均などの店々。通りを進んでいくと、『ボードゲームで遊べる!』と白文字で書かれたプラスチック製の黒い置き看板を見つけた。
その下の『中学生以下は0円!』『水曜日はレディースDAY!』という文字の他に、ピンクや緑のペンでバラが描き散らされている。
「ここみたいだな」
父の言った通り、小さい店だった。
白塗りの壁、クリーム色の看板がかかった木のドア。看板には、不揃いな木の枝で『ボードゲームカフェ・ミナクル』の文字が作ってある。
ドアの横にはガラス張りの細長い窓があり、そこからは店の中が何となく見えた。
フローリングの床の上に椅子・テーブルが何組か。奥のカウンターには店員と見られる人物が立っている。白い鳥打帽を被り、首にも白いバンダナを巻いた男性で、手元の書類にじっと目を通していた。
「いるいる。お邪魔しまーすっと」
父が軽い手つきでドアを押し開くと、頭上のベルがカラカラと音を立てた。カウンターの男性が顔を上げ、書類を仕舞ってニッと笑った。頭の帽子を手に取り、大げさな身振りでお辞儀をする。
「いらっしゃい、ソラくんさま」
「遊びに来たよ、ヒロ」
「嬉しいなぁ。そっちの子はもしかして葵ちゃんかな?」
名前を呼ばれて思わずドキッとしてしまった。両親以外の人に下の名前で呼ばれるのに慣れていないからだ。
おずおずと父の後ろから顔を覗かせる。男性は腰をかがめ、えくぼを浮かべて葵を見ていた。
初対面の知らない人だ。だから結構緊張している。でも、父親の友達とあれば挨拶をしないわけにはいかないだろう。
「初めまして、空山と申します・・・」
言ってから、この挨拶はおかしい、と気づいた。父親と男性は顔を見合わせて噴き出した。
「うんこんにちは、空山葵ちゃん。・・・ってあれ、流石に覚えてないか。もう十年くらい前だっけ」
「えっとね葵、このヒロおじさんはね、葵が小さい頃何回か会ってるのさ。昔、この町に住んでたから」
「そうそう。それであちこちウロウロしてからまたこの町に戻って来たってわけさ」
「てかヒロ、お前県外に丸太小屋作ってなかったっけ。あれ、今どうしてるんだい?」
「キシくんに貸したよ。細君と二人で山に住むのが夢だって言うからさ」
挨拶が済んでしまうと、父親と友達はお互いの方を見てぺちゃくちゃしゃべり始めた。葵には分からない、ついて行けない話だ。いつもながら、こういう時って本当にどうしていいか分からない。
葵は二人の傍を離れ、店内を見回した。四つテーブルとそれを囲む椅子が置かれたこじんまりとした空間。左右の壁は一面が棚になっていて、上から下までボードゲームがびっしりと敷き詰められている。
(すごい・・・)
葵の部屋の本棚と図書館を比べた時と同じギャップを感じた。我が家にあるボードゲームなどたかが知れているということだ。
上を見上げればそこは吹き抜けで、深緑のカーペットの上にニンジン色のソファーが置かれているのが見えた。店の奥の階段で上り下りできるようなので、二階も利用できるということだろうか。
ボードゲームはいっぱいあって、店内の雰囲気は優しい。外に出るのはあまり好きではないけれど、ここではまあまあ居心地よく過ごせるかもしれない。
「ところで、客足はどうなんだい?」
「まあ、まだオープンしたばっかだからさ・・・っとといけない。葵ちゃん、早く遊びたいよね。説明に入ろうかな」
白帽子の男性は小走りでカウンターの中に戻り、コホンと咳払いした。
「改めましてお二人さん。ボードゲームカフェ・ミナクルへようこそ。僕は店長にして唯一の従業員、ヒロです」
「おお、ぽいぽい」
「ここには、300個以上のボードゲームが置いてあるよ。どれでも好きなのを自由に遊んでオーケー。遊び方が分からなかったら聞いてくれればいいからね」
「うんうん」
「料金はここに書いてある通り、一時間につき六百円。葵ちゃんは中学生だから無料だよ」
「だそうだよ、良かったね葵」
「無料といえば、うちはドリンクバーが無料だから。そこで自由に注いでいいからね」
カウンターの横にある、二台のドリンクサーバーを指さしながら言う。コーヒー、お茶、ジュースなど、ボタンを押せば好きなドリンクが注げるらしい。
「料理も注文できるよ。別途、料金はかかるけどね。いつかお腹空いている時に、カレーを頼んでくれたら嬉しいな」
「そう言えばこいつ、スパイスに凝っててさ。今度来た時頼んでみないか?」
「『美味しいけど、パパほどじゃないね?』とか言うつもりなんだろ?」
「ははっ。バレたか」
「まーまーせいぜい不安になってな。で、これも渡しておかないとな」
長方形のカードを二枚、カウンターの上に出した。真ん中に折り目がついた、二つ折りするタイプの厚い紙のカードだ。1から50までの小さい数字が入った白いマスが、すごろくのように左上から右下へと続いている。5,10,15と5の倍数のマスだけカラフルな花形で、何か特別感がある。
店長は1のマスのところに今日の日付を書き込んだ。
「ポイントカードだよ。来てくれたらどんどん埋まっていく。お花のところが埋まったら、次回以降使える特典をプレゼントだ」
「割引とかかい?」
「それもある。最初の方は『串カツ3本』みたいな食べ物系だけどね。詳しくは裏に書いてあるから確認してみてくれ」
葵はカードをつまんで裏返してみた。なるほど、「ピザチケット2枚綴り」「50%オフ」など様々な特典があるようだ。
ふと葵は、その特典一覧の折り目を挟んだ反対側に目をやった。何も書かれていない、白くて大きい枠がある。一体これは何なんだろうか。まさか落書きでもしていいよ、というのだろうか。
「そこは名札さ。ニックネームを書いて首から下げてもらう」
葵の目線に気づいた店長が油性ペンを二本取り出しながら言う。
「ニックネーム、ですか?」
「うん、この店の中ではお互いニックネームで呼び合う決まりがあるからね」
じゃあ「葵」「パパ」と呼び合えないのか。なんだか不便な気がする。
「なんでかっていうとね・・・」
カラカラカラン。
ベルが鳴る音とともに、どたどたと誰かが店内に踏み入って来た。
「こんちは、ヒロ店長」
「今日も来ちゃいましたー」
元気良く挨拶したのは男女二人組だった。葵から見たら「お兄さん」「お姉さん」っぽく見える年頃の人達だ。
「いらっしゃい、[みかん]さん、[オレンジ]さん」
腰に上着を結び首にヘッドホンを掛けた男子と、化粧の濃い金髪の女子。大きな黄色い星マークの入ったシャツをお揃いで着ている。よく見たら、女子の方は大きな星のピアスも付けている。苦手な人達かも、と葵は思った。
そんな男女は、葵と父親を見て目を丸くした。
「あ、他のお客来てる。こんちはっす」
「こんにちはー」
「こんにちは」
「こ、こんにちは」
まさかこっちにまで挨拶してくるとは思わず戸惑ったが、とりあえず父親に倣って挨拶を返した。
「とりあえず、3時間でおなしゃす」
「うんうん了解。多分今日も、延長は大丈夫だと思います」
店長が首からぶら下げるカードホルダーを渡すと、二人は手慣れた動作で二つ折りにしたカードをそこに入れた。
「他のお客さんに会うの初めてだな~常連だったりするんすか?」
「いや、僕らは今日初めて来たところさ」
「あ、なるほど」
「今日はついてたわね」
「な~。だって店長入れて五人だもんな」
「ああ、ごめんなさいね。僕はまだちょっと参加できないの。開店したばっかで色々と手が離せなくて」
店主がごめん、というように手を合わせる。
「ちぇ、またっすか」
「そんなんじゃ、おひとり様は来ませんよー」
「すいませーん。一週間ぐらい後に、こちらからお手合わせ願いますので」
「分かりました。約束っすよ?」
「じゃ、四人で遊びますか。何かやりたいゲームとかってありますか?」
と、真っ赤な唇が聞いてきたので葵は目を泳がせた。
(えー困る困る困る)
当たり前のように葵と父親を数に入れてくるが、勘違いであってほしかった。ボードゲームは父親以外とは遊ばない。知らない人の、しかもこんなチャラそうな人達の相手をするなどまっぴらごめんだった。
「ここでは他のお客さんとの相席もオーケーだよ。ニックネームを用意してもらうのはそのためさ」
葵の期待を裏切り、店長が話の続きを始めた。
「ウチじゃ、日曜日は相席をお願いすることにしてるんだ。まあ今日はどっちでもいいんだけどね。どうする? 人数多い方が楽しいと思うから、相席してくれたら嬉しいんだけどな」
(イヤです)
と思っても口に出せるわけがない。葵は縋る目で父親を見上げた。
「折角だし、相席してみない?」
葵は唇を強張らせ、背伸びをして耳元でひそひそ囁いた。
「カップルかもよ。邪魔したら悪くない?」
「だったら自分達からやろうよって誘わなくない?」
「う、う~ん・・・」
反論が思いつかずパチパチとまばたきする葵を置いて、父親はニコニコ笑いながら二人に近づいていく。
「ぜひご一緒させてください」
「やったー! じゃあ、ゲームを選びましょー」
「これやらね?」
と男子の方が何かを出してきた。両手に乗るサイズの箱だ。オレンジ、黄色、ピンクと割と明るい色をしている。
「前遊んだじゃないの」
「でも結構良くなかった?」
「まあ、それはそう。お二人が良ければこれにしましょう」
箱の表面には「最高のごちそう」のタイトル。その下に、ナイフとフォークを構えたひげもじゃの王様、ネックレスをつけた肥満体系のパーマ女性、ハンバーグの乗った皿を高く掲げるドヤ顔のコックのイラストがある。
見覚えがある、と葵は思った。
「あれ・・・これウチにあったっけ?」
父親が首を傾げてきたので、葵はこくんと頷いた。やったことがあるような気もする。全然覚えていないけれど。
「あ、別のにした方がいいっすか?」
「いや、遊んだのは結構前だからどんな内容かは忘れてるよ」
棚に戻そうとする男子を押しとどめ、父親は葵の方を向いた。
「初めてのつもりでやってみる?」
こくん、とまたしても葵は頷いた。
「決まりですね。じゃあ、ここでやりましょー」
女子に促され、四人は近くのテーブル席に着いた。
「じゃあ準備を、ってまず、自己紹介からっすね。俺[オレンジ]っす」
「ギャグのつもり? 私は[みかん]っていいます」
「初めまして。僕は[ソラコック]です。ソラって呼んでください」
と、間髪入れず父親が自己紹介をしたので葵はギョッとした。なんと、[ソラコック]と書かれた名札を持ち上げて自己紹介しているではないか。
いつの間に書いていたのだろうか。なんだか置いて行かれたようで少し恨めしい。
[みかん]と名乗った女子が肘をついて首を傾げてくる。
「あなたはなんていうの?」
「スカイ・ブルイです」
キュッキュとマジックで書きながら答えた。つまらない名前だと思われたろうが、とっさに考えたんじゃこんなものしか思いつかない。
「オッケー。ソラさん、ブルイちゃん。じゃあいよいよゲームを」
「あーちょっと!」
突然、カウンターから店主の大声が上がった。たちまち四人の視線が集まる。店主は申し訳ないというように帽子を持ち上げ、カウンターの外へ出て窓の方に歩き出した。
「どうしたんだい、ヒロ」
「いえね、今カートを置いてかれたのさ。ウチの前に」
腰を浮かしてみると、確かに窓の下にスーパーでよく見るカートが置き去りにされている。
「うーっわ、酷いっすね。やったのあいつらですか?」
窓の外を悠々と歩き去る金髪の男女。背が高いので外国人だろうか。
「ちょっとごめんね、注意してきます」
店長は店の外に出ると、走って外国人二人を呼び止めた。時折頭を捻りながらも、身振り手振りでカートのことを伝えているようだ。
「ヒロ店長、大丈夫かしら。逆ギレされたりしない?」
だがすぐに、外国人二人はぺこぺこと頭を下げた。店の前まで戻ってきてカートを引く。
店長も一緒に戻ったが、ドアを開けて顔だけ出すとこう言った。
「どこに戻していいか分からないんですと。案内しなきゃいけないみたいなので、少し店を空けます」
「いやそれはまずいだろ、僕が行くよ」
と席を立ったのは葵の父親だった。
「いや、お客さんにそんなことさせたら悪いよ」
「店主が店を留守にする方が悪いよ。それに今忙しいんじゃなかったのかい?」
「う・・・ん。そうだな、すまん」
「こういうことがこの先もあるかもしれないし、さっさとバイトを雇うことをお勧めするよ」
「ああ、申し訳ない・・・」
「と、いうわけでだ。三人で遊んでてくれないかな」
葵が口を挟む暇もなく、父親は店の外へと飛び出していった。
(えー・・・)
去っていく父親を前に葵は途方に暮れた。この状況でも、父親がいるからまだ耐えられたのに。
(初対面のチャラそうな人達を、一人で相手しなきゃならないなんて・・・)
「ソラさん、すごいわね」
「ナイスガイよなー」
葵の胸中など知らない二人は、彼女の父親を称賛しながら箱を手に取った。
パカッと箱の蓋が持ち上がり、纏められたカードやら袋に入ったチップやらが姿を現した。
「じゃ、ゲームを始めましょうか!」
ーー
まごまごしている葵を前に、男女はてきぱきとゲームの準備を進めていく。
まずテーブルの上に山札を4つ裏向きに並べる。「お客様」と書かれた緑色のカードの山札、「食材」の茶色の山札、「今の気分」の水色の山札、そして黄色と赤の縞模様の「チェンジ」の山札。
続けて男女はA4くらいのサイズの厚い台紙を1枚ずつ各々の前に置いた。台紙は3枚とも色が違うが、どれもパステルカラーでランチョンマットのような見た目をしている。
台紙の中央にはカードを1枚置ける大きさの枠が5つあり、端には1から10までの数字が入ったマスが一列に並んでいる。
1のマスに星形の駒が置かれた時、葵はこれがどんなゲームだったか思い出した。
(これ、あんまりおもしろくなかったやつだ)
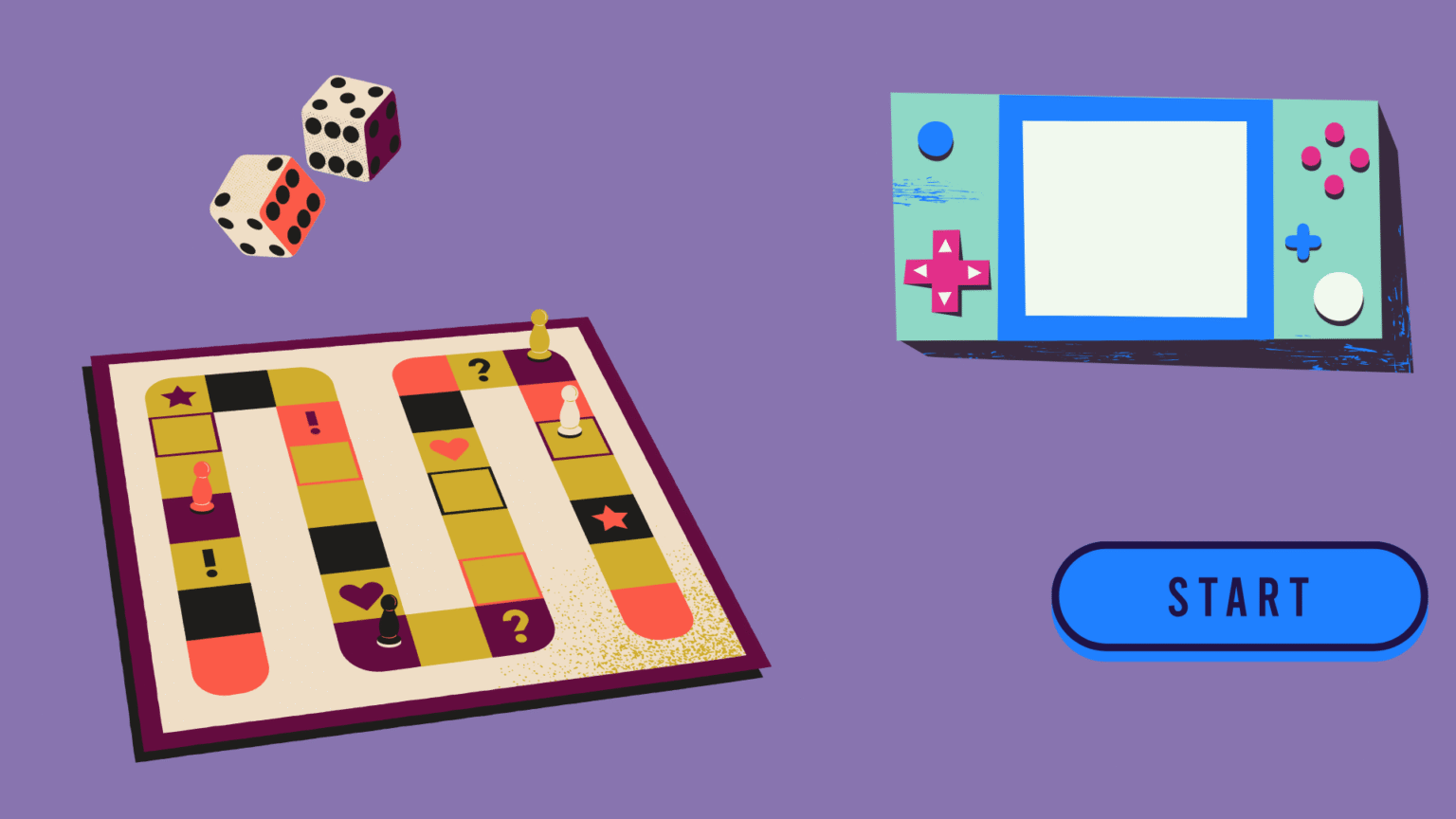

コメント