「マッシー遅すぎ~」
頬杖をついていた萌々がついに立ち上がった。
「まだ弟くんにお説教してんのかな~。見に行こーよぉ」
「同じこと思ってた」
翠も立ち上がる。眞代が抜け、ゲームを中断してから結構な時間が経った気がする。いい加減に戻ってきて欲しい。
「さっきさー、〈聖杯〉ゲットしたんだよね」
「え、うそ、新アイテムじゃん、いいなぁ~」
「眞代、〈磁石〉持ってたから連携すればキラーを倒せるはず」
言いながら、翠はワクワクしていた。自分の手でゲームを勝利に導けるのは勿論、新アイテムや連携技が使えるチャンスが目の前にあることにだ。
パートナーが眞代というのが不安だが、そこは自分のフォローで何とかしてみせる。
襖を開け、廊下に出る。リビングと思しき部屋の襖の奥から話し声がする。
「うちの噂のせい? あーそれともアレ? はやりのテレビゲームに夢中なの、友達?」
「うん・・・」
「あーなるほど、この家にはゲームなんてないからな。それなら行かなくていいってなるね」
なんだか長話の予感がする。
新アイテム、連携技。その二つが頭の中でぐるぐるして落ち着かない。
「まし」
「ミドリン、ストーップ」
襖を開けようとしたところで、萌々に止められた。
「終わったら声かけよ」
「えー待つの? 待たなきゃダメ?」
うんざりしながらも翠が襖から手を離したその時だった。
「てかそもそも姉さん、ゲームはあんまり好きじゃないでしょ」
体が、動きを止めた。
(え、眞代がゲーム嫌い?)
聞こえてしまったその言葉に、頭がついていかない。
(嘘、嘘だ・・・)
『コビトレジャー』、『キラーを殺せ』、『Sir. Bibal』。何度も何度も遊んできた。ずっと三人で、最近では四人で、たくさん勝って負けて笑って盛り上がった。
なのに、眞代がゲーム嫌いなんてそんなことあるわけが・・・。
(そんなわけないって言ってよ、早く)
だが、襖の向こうからは、否定の言葉は出てこなかった。
(眞代・・・本当はゲームするの嫌だったんだ)
放心状態になった翠を他所に、扉の向こうで会話は続く。
「なんでもいいけど、僕には理解できないな。『召使い』なんかが大事なんてさ」
「ちょっとミズハ! その話は・・・!」
バン、と傍で木が激しく打ち付けられる音がした。立ち尽くす翠を置いて、萌々がずんずんと居間の中に入っていく。
(え、何・・・召使い・・・あ、萌々のことを言ってたわけ? え、何その話・・・)
ぼんやりと、そんなことを考えていた。そんな、どうでもいいことを考えずにはいられなかった。
騒々しい居間を背に、翠は一人客間へと戻った。手提げかばんを持ち、自分のMSGを仕舞う。そして、眞代に貸したMSGにも手を伸ばす。
『もうあたし、ゲームなんて興味ないから』
かつて投げかけられた言葉が頭をよぎった。
小学生の頃、一緒にMSGを買ってもらった姉。ずっと二人でゲームをして遊んでいたのに、中学に上がった姉は同級生と出掛けることに夢中になった。
(眞代だって、眞代だって・・・)
ずっと一緒にゲームで遊んでくれると期待していた。でもゲームが嫌いなら、いつかは翠とゲームをするのを嫌がるに違いない。
頭がカッと熱くなり、足元がじんじんと震えてくる。フーッフーッと息が荒くなっていくのを止められない。
翠は姉のMSGを掴み、玄関へと向かった。リビングの喧騒には見向きもせず、眞代の家を飛び出した。
家に帰っても、翠の苛立ちは収まらなかった。気が付くと、感情のままにこんなことを書き殴っていた。
『ゲーム好きって言ってたのに嘘つき。イヤイヤやってるんなら、もう一緒に遊ばなくていいから』
そして翌日、眞代の机の中にそのメモを置いた。
(もういい、こっちから願い下げだし!)
その日、眞代とは口を利かなかった。
(萌々と二人で遊べばいいし)
「あ、萌々。あのさ」
「・・・」
だが、萌々に話しかけても無視された。萌々は喧嘩したらしい眞代は勿論、翠のことも避けているようだった。
◇◇
(ホント最悪、ミドリンにまで昔のことがバレちゃうし・・・)
電気のついていない部屋で、萌々はベッドにうつ伏せになっていた。寝てはいない。眠れるわけがない。
萌々がいわゆる”パシリ”だったこと。それを誰かに知られるのは、『Sir. Bibal』のセーブデータを全部消されるのと同じくらい耐えられないことなのだ。
■■
小学四年生に進級した春、萌々だけが眞代や翠と離れて別のクラスになった。
「毎日お喋りしよ!」
眞代はそう言ってくれても、学校にいる間はほとんどずっと別々だ。
とはいえ、別に萌々はクラスで孤立したりしなかった。眞代や翠ほどではないにせよ、なんとなく仲良くしている女子は何名かいたし、三人組のグループに入れてもらうこともできた。
二人一組や移動教室で困らなかったのは勿論、休み時間には机の周りでお喋りし、放課後も四人で集まって遊んだ。
遊ぶのはほぼ毎日で、少し驚いたが早々に慣れた。萌々も自然と彼女たちのペースに溶け込み、新しいグループでの生活を楽しむようになった。
「バニラとチョコ二本ずつあるね」
「急いで買お!」
週に一度、こっそり買い食いもした。先生の目を盗む、というのがこれまた最高のスリルだった。
そう、とても楽しかった。最初のうちは。
「わー、チーちゃんすごい! また100点じゃーん!」
「ふふん、軽い軽い」
「モモちゃんは0点?!」
「えー、0点なんて初めて見た~」
「え、えへへ~。びっくりしたぁ?」
テストが返ってくるたび、「いっせーのーで」で答案を見せ合うルールがあった。グループのリーダー・千奈津が決まってトップで、ビリは毎回萌々だった。この頃から既に萌々の成績は酷いもので、テストは最高でも15点。一桁を取ることが多かった。
学力だけではない。運動も苦手で、特技と呼べる特技も何一つなかった。
「モモちゃん、50m11秒は遅すぎ~」
「水のり多っ、絵がベタベタじゃん」
勉強ができないのも、運動音痴なのも、手先が不器用なのも、それまでは何とも思わなかったのに、この頃は恥ずかしくてたまらなかった。毎日毎日、萌々がグループの中で一番下だということが明るみにされる。そのせいで萌々は委縮し、今までになく大人しくなった。
そんな萌々は三人にとって格好の標的であり、何かにつけて「格下の萌々」いじりをするようになった。
「じゃ、答案オープンするねー! いっせー・・・」
「あ、待って待って。その前にさ、みんなでモモちゃんの点数当てっこしない?」
「いいねー、私0点だと思うー!」
「私もー」
「いやいや、流石に今回は違うでしょー。私はモモちゃん史上初の20点到達に賭けるわー」
「おおっ、もしかしてもしかすると~。さあモモちゃん、答案オープン!」
「さ、3点だった~。あはぁ・・・」
「あーん、みんなハズレー」
「てか逆にどこが合ってたのー?」
皆がキャッキャと騒いでいる中、萌々はにへらっと愛想笑いをしてやり過ごした。ちっとも楽しくなかったのに。
どうすれば、いい点数が取れるのかと聞いてみたこともあった。だが。
「いやいや、モモちゃんはおもろいからそのままでいてー」
口を揃えてそう言う。要するに、これが萌々のグループ内でのポジションなのだ。三人の下に、ずーっと下に萌々。
この暗黙のルールが浸透し始めると、ついにパシリにされた。
「これ、私のロッカーに置いて来てくれない?」
「え~、今日水やり当番~? モモちゃん、代わりにお願いしていい?」
「モモちゃん、宿題・・・はいいかな。間違いだらけになっちゃうもんね」
何をさせられても言われても、萌々は不満一つ言わなかった。一緒に遊ぶことは楽しかった。だからどちらかというといい友達には違いなかった。
それに、女子社会では空気を壊すことがタブーだとちゃんと分っていた。自分のポジションをちゃんと理解して振舞わなければならないことも。
(モモ、何をやっても駄目だからなぁ・・・。仕方ないよね・・・)
そんな萌々に転機が訪れたのは、10月の半ばのこと。ある日の放課後、萌々はあるものを探すために裏庭の茂みに一人しゃがんでいた。
「萌々ー? そんなところに何してんの?」
背後から懐かしい声が掛けられる。見慣れたポニーテールの少女がバケツを片手にこちらに近づいて来た。
「マッシー。あの、ちょっとピン探しててぇ」
「え? ちゃんと髪についてるよ?」
「モモのじゃなくってぇ、チーちゃんのピン。なくしちゃったみたいで・・・」
えへへ、と笑うがその顔はややこわばっていた。茂みから手を出し、冷えた指先をすり合わせる。
「え、千奈津ちゃんのピン? じゃあ、何で千奈津ちゃんは探さないの?」
眞代はバケツを地面に置いて、萌々の傍にしゃがみ込む。そしてじっと目を合わせて来た。密着しているせいか、少し温かいような気がした。
そういえばずっとグループ行動ばかりで、こうして眞代と顔を合わせるのも随分久し振りだった。
「寒いのが嫌みたいでぇ。それでモモが代わりに」
「何それ、意味分かんない」
「えっとぉ、まあそれがモモのポジだから」
「まさか、今までもこういうことさせられてたわけ?」
眞代の声に怒りが籠る。次の瞬間、萌々は両肩を掴まれ上に引き上げられていた。
「千奈津ちゃんのピンなんだから、千奈津ちゃんが探すべきでしょ! そんなふうにいいように使われてさ、みっともないと思わないの?!」
眞代の怒りは、目の前の萌々に向けられていた。萌々の体にすっと冷気が戻る。
(モモだって、したくてしてるわけじゃないのに・・・)
パシリにされるわ怒られるわ・・・。何故自分ばかりがこんな辛い目に合わなければならないのか。
急に何もかもが腹立たしくなってきた。
「千奈津ちゃんは良くないよ。だからもうさ、」
「分かった。もうチーちゃん達とつるむのをやめる」
「うん、絶対その方がいいよ」
眞代は打って変わって満面の笑みで頷き、萌々の肩から手を離した。
「じゃあ今から職員室行こ! 先生に、千奈津ちゃんのこと叱ってもらわなくちゃ!」
ドキリとした。同時に「イヤだ」と思った。
「あ、それは大丈夫かなって」
「なんでよ」
「誰にも言ってほしくないのぉ」
「意味分かんない」
「えへへ、ごめーん。でもお願いマッシー、このことは絶対誰にも言わないで。ねっお願いー」
お願いポーズの両手を、顔の前でグネグネさせて眞代の顔を見上げた。彼女はというと、困った、という顔で萌々を見ている。
「その約束はちょっと・・・」
「いいじゃーん。モモ、マッシーの言う通りちゃんとあの子達から離れるよぉ? マッシーもモモのお願い聞いてよぉ」
「うん、分かった・・・」
まだ何か言いたそうな眞代ににへらっと笑みを向ける。
「モモもう平気だよーん。じゃあね、バイバーイ!」
「あっ、萌々」
立ち尽くす眞代を置いて早足で校舎へと戻った。今は眞代の傍から離れたかった。
彼女の前では笑っていたが、惨めな気持ちでいっぱいだった。何が惨めなのか、何故惨めなのかも分からない。ただ忘れてしまいたかった。何もかも。
その日は帰るなりベッドに直行し、うつ伏せで朝まで眠った。次の日も、その次の日も、何となく学校に行く気にならず休み、そして土日を挟んで月曜日。
なんと、千奈津が学校を休んでいた。家の用事だという。グループの二人は、ムードメーカーの彼女がいないせいか妙に大人し気で、モモを見ても話しかけてはこなかった。
千奈津が転校する、と知ったのは翌日の朝の会だった。千奈津は、お別れ会の日までもう学校に来ない、とも先生は言っていた。思わずドキッとしたが、その後特に萌々が先生に呼び出されるようなことはなかった。
(マッシーがモモのことをバラしたわけじゃないんだ)
ホッとした。モモがパシリだったことは誰にも知られない。そして千奈津はもういない。
これで全部忘れられる、と思った。
こうして、なし崩しで千奈津のグループを抜けた萌々。クラスの女子と適当に付き合いながら、眞代や翠ともたびたび遊ぶようになった。
「これ、やりたいんだけど」
翠の家に集まったある日、萌々は初めてテレビゲームを見た。空の上や夢のお城を、可愛い絵柄の小人が上下左右にちょこちょこ移動する。敵を倒しながら、ピカピカ光る宝石の欠片を集めて点数を競うゲームだ。
「うわ、なにこれ楽しー!」
萌々はたちまち夢中になった。指を弾ませてボタンを押し、宝石を集めては敵に弾を浴びせた。敵に弾が命中した時は、思わずコントローラーをブンブン振ってしまうほど興奮した。
この日が初プレイだったにも関わらず、最後の方はあとちょっとで翠に届きそうなほどスコアが伸びた。
「あーん。もうちょっとだったのにー」
「惜しかったねー、でもすごいよ萌々」
「あたしも認める。才能あるよ」
「えっ才能?」
萌々は手元のコントローラーを見、それからゲーム画面に目をやった。
355点のスコア。
(あれが、モモの点数・・・)
その下には、プルプル動く「Game Start」のボタン。時折光沢が走るそれは、まるで萌々に誘いをかけているかのようだった。
「ねえ、もう一回やろーよぉ」
その日は、眞代が音を上げるまで何度も何度も再戦をねだった。
帰宅した萌々は早々に誕生日プレゼントをリクエストし、後日ゲーム機を手に入れた。その日からは、家に帰って『コビトレジャー』をやりこむ日々が続いた。
遊べば遊ぶほど腕前が上がり、難しそうに見えていた1000点台にもあっという間に乗った。
「あれ、ひょっとしてモモすごい?」
嘆いても嘆いても、テストで0点ばかり取っていた自分とはまるで別人だった。
萌々はどんどんゲームにハマり、三学期になると自分から眞代や翠にゲームを紹介するほどになった。
「どっちやりたいー?」
「へー。萌々もゲーム買ったんだー」
「うん。『キラーを殺せ』はサンタさんから、『Sir. Bibal』はお年玉で買ったんだよぉ」
テレビゲームで遊んでいる時が一番楽しかった。高いスコアを取るたび、上手いと褒められるたび、嬉しくてたまらなかった。
(モモ、今すっごくキラキラしてる!)
こうして三学期も瞬く間に過ぎ、小学五年生を迎えた春。
「今年は三人一緒か」
「やったね萌々!」
「うん、二人ともよろしくぅ!」
また、三人で一緒に過ごす時間が戻って来た。だが。
「漢字テストって、どんな問題が出るんだろうね。勉強会しとく?」
「う~ん、別にいいかなぁ。モモ、バカだからどうせ0点だもーん。それより、『キラ殺』の新ステージ解禁しなきゃ」
「今日は天気がいいから外でボール遊びしない?」
「え~。それより『Sir. Bibal』の続きやりたーい!」
見ないふりをしているだけで、少しずつ歪みが生じていたのも事実だった。
■■
(イヤなこと思い出しちゃった)
萌々はベッドでうつ伏せになったまましばし脱力していた。
(忘れよっと)
一瞬だけぎゅっと枕に頭を押し付けた後、マットレスを押してぐんと体を起こす。ジャンプして床に着地したところで、何かを踏んづけて足の裏にじんと痛みを感じた。
「いたっ」
放りっぱなしのMSGだと思う。今の衝撃でどこかに飛んだが、部屋が暗いのでどこに行ったか見えない。
「ま、もうどうせ使わないしいっか」
足元に気を付けながら、机の横の小型テレビをつけてゲームを起動する。暗い部屋の中で、見慣れた『コビトレジャー』のホーム画面が明るく照らし出された。
画面下部には、これまでの最高スコア、100100点。萌々のゲームのレベルはここまで到達している。
「別にいいんだもん・・・。だってモモ、ゲームが上手いんだから・・・。だから・・・」
そこから先は言うのをやめた。あの時の、裏庭で感じた惨めな気持ちが心を覆っていきそうだったからだ。
無言で「Game Start」のボタンを押す。そして萌々は、ぱあっと輝く『コビトレジャー』の世界に入っていった。
◇◇
「・・・オイー、葵ー」
名前呼ばれているのだと分かりハッとした。キッチンの奥から、父親が心配そうにこちらを見つめている。
「ごめん、ぼーっとしてた」
ここ最近、ずっとこんな感じだ。
「もしかして体調悪い?」
「ううん、そんなことないよ」
「なら良かった。ちょっとパパに付き合ってほしいんだけど」
そこで葵は初めて、父親が珍しくショルダーバッグをしていることに気づいた。
「え? いいけど、どこに行くの?」
「ボードゲームカフェ」
「へ? ボードゲーム、カフェ?」
思わず、ポカンと口を開けてしまった。
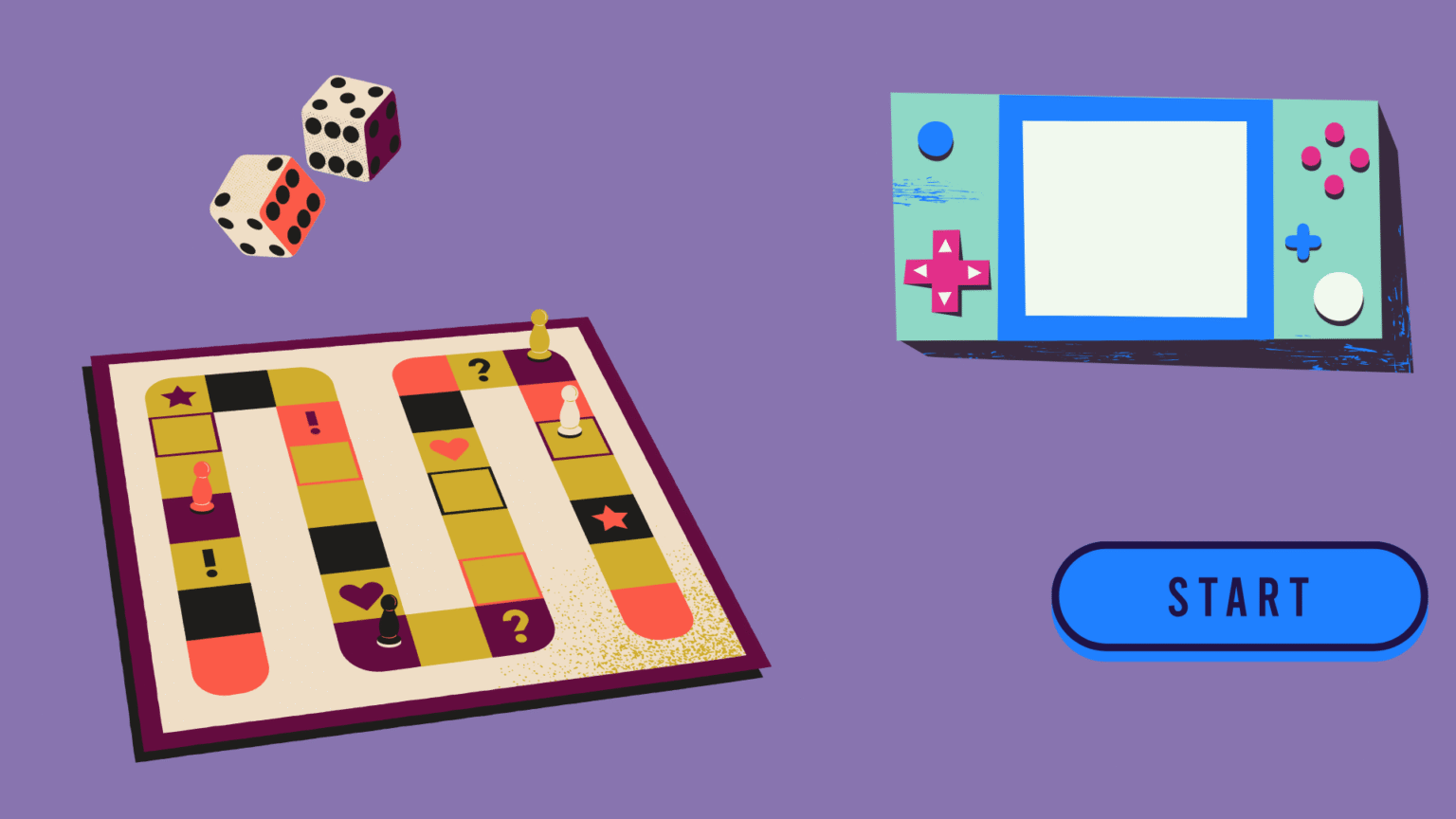


コメント