「葵ちゃーん」
教室の外から自分を呼ぶ声がした。ポニーテールの少女が教室の後ろのドアからこちらに手を振っている。葵は読みかけの本を閉じて駆け寄った。
「眞代ちゃん、おはよう」
「おはよー。何読んでたの?」
「グリム童話Ⅱ」
「あれ? おととい読み終わったんじゃ?」
「貸出期間いっぱいまで読み返そうかなって。内容全部覚えちゃうまで」
「ホント好きなんだね」
笑う眞代。
「そういえば私もね、イソップ寓話借りてみたんだよ。葵ちゃんが勧めてくれたから」
「! どうだった?」
「まだ途中なんだけどね、一個一個の話が短くて読みやすいよね。あと、知ってる話がまあまああった。『北風と太陽』とか『ウサギとカメ』とか。昔絵本で呼んだことあるから、すっごい懐かしい気持ちになったなぁ」
「あーなるほどね」
「でも知らない話のほうが多かったよ。あっ、てかなんかさ『狐と葡萄』って話あるじゃん」
眞代が廊下側から身を乗り出してくる。軽く内緒話でもするような姿勢なので思わず葵も耳を近づけてしまう。
「あれ、塾の英語のテストに出たんだよね」
「ほお」
「文章問題だったんだけどね。ストーリー知っちゃったから、あんまり訳す必要なくってさ。時間が10分も余っちゃった」
「それはラッキーだったね」
「そうそう、だから葵ちゃんには感謝! でもちょっとズルしちゃってるから、他の人には内緒だよ」
いたずらっぽく笑い、人差し指を口に当てる眞代。その可愛らしい仕草につられ、葵も笑みを浮かべて頷く。
「眞代ちゃーん、何してんのー」
突然、隣のクラスの生徒から呼び声が掛かる。
「塗り絵上手くできたよー見てあげてー」
「はあい、待っててねー」
顔だけそちらに向けて応えた眞代は、葵の方に向き直り申し訳なさそうにする。
「もうちょっとお喋りしたかったけど、呼ばれちゃった。ごめんね。えっと、伝えなきゃ。次のことなんだけどさ」
眞代は表情を改め、ドアから体を離した。
「明日、翠の家でどうかな?」
「うん、大丈夫だよ」
「了解、二人にも伝えとくねー」
手を振り、くるりとターンバックする眞代。ポニーテールが軽やかに跳ね、後ろ姿が隣のクラスに消えていく。葵はドアから身を乗り出して見送り、早足で自分の席に戻った。
席に着くと、読みかけの本を放置したまま少しの間足を浮かせ宙を見ていた。今のほんのわずかな時間の余韻に浸っているのだ。
(遊びに誘われる私・・・ムフフ)
「今日遊びに来ない?」「うん行く」そんな仲良し同士の会話を、読書しながら聞き流していた自分が、まさか当事者になるなんて思いもしなかった。
社会見学の日からもうすぐ三週間になる。あれから週に二日ほど、萌々か翠の家にお邪魔している。同じクラスの三人が相談してそれを眞代が葵に伝えに来てくれるのだ。さっきのように、雑談を交えてくれながら。話題は大抵、葵が読んでいる本のこと。他の話ができる気しないので、そういう話題を振ってくれるのがとても助かる。
まあともかく、さっきのような会話をするのは初めてではないのだが、これまでの人生で馴染みがないことすぎて気分が高揚してしまうのだ。
(今の私はもうぼっちじゃないんだな・・・)
しばらく「今の私」を嚙み締めていた葵だが、ふともうすぐ休み時間が終わることを思い出した。浮かれた気持ちを引き締め、読みかけの本をバッグにしまう。
机の中から教科書を引っ張り出しながら葵は思った。
(私もそろそろ、家に呼ばなきゃだよね)
□□
「友達はウチに来ないの?」
昨日の夕食の席で父親にそう聞かれた。
「う、うん。皆、萌々ちゃんか翠ちゃん家がいいみたいで」
「でも、人の家にお邪魔してばっかじゃ悪いでしょ」
レモネードをグラスに注ぎながら母親が口を挟んでくる。
「たまにはウチに呼びなさいよ。遊ぶものならちゃんとあるでしょ」
葵はリビングの壁を見やった。
「その子達、ゲーム好きなんだよね? ならきっとボードゲームにも興味を持ってくれるさ」
葵の心配を察したように父親は優しい言葉を掛けてくれた。
それに対し、葵は曖昧に頷いたのだった。
□□
ーー
「やったぁ、モモが一位だぁ!」
リモコンを持った手をめいっぱい伸ばしてガッツポーズする萌々。その横で翠は頭を抱えている。
「最後、ボム作らなきゃよかった・・・ついいつもの癖で・・・そうだよこれ『Easy』じゃん、うっかりしてたわ・・・」
「惜しかったね、翠。このステージもう一回リベンジする?」
「いや、別ステージが良いかな」
「えー、じゃあその後は『キラ殺』にしてよぉ?」
(三人とも、ホントにテレビゲームが好きなんだね・・・)
これまで、例の小人のゲーム『コビトレジャー』の他に、キラーvs逃走者で殺し合う『キラーを殺せ』、四人で力を合わせてサバイバルをする『Sir. Bibal』の三つのゲームを代わる代わるプレイしてきた。そう。初めて遊んだ日からずっとテレビゲームをしているのだ。
こんなにテレビゲームにハマっている子達が、ボードゲームに興味を持ってくれるだろうかと不安ではある。
(でも・・・ゲームが好きならボードゲームだってやるかもしれない・・・)
昨夜の父親の言葉に縋りたくなってしまう自分がいる。意を決して葵は口を開いた。
「さ、三人ともさ」
三人の目線が一気に葵に向く。
「ほ、本当にテレビゲームが上手いよね」
なんだか日和った切り出し方になってしまった。
「なに~アオイっち今更~」
ジュースを一口飲み、萌々が笑った。
「当然でしょ、私達はずっと前からやってるもの」
翠が肩をすくめた。
「そーそー。モモ達、この三つに関してはもはやプロだよねぇ」
「小学生の頃からのお気に入りだよね。『Sir. Bibal』なんて、前とその前の主人公のストーリーもクリアしてきたもんね」
感慨深げに頷く眞代。
「アオイっちは知らないと思うけど、前の前の主人公のリメイク前のはグラフィックがポリゴン系でさ。めっちゃ見にくい中プレイしたんだよ」
「ほ、ほーん。そうなんだ」
話について行けないのと、自分の望む方向にどう持っていこうか悩むあまり適当すぎる返事になってしまった。マシロが気遣わしげな表情を見せる。
「大丈夫だよ葵ちゃん、やってれば上手くなるから。と言うか、私のことはすぐに追い越すと思うよ」
「あはっ、かもね。でも、モモより上手くなるのは無理だけどねぇ。だってモモ、一人の時もゲームしてるもんね」
「そうなの?」
「うんっ。プチクエスト的なのやって、アイテムゲットしたりステージ解禁したりしてるよぉ」
少し誇らしげな萌々。
「正直、『キラ殺』と『サーバ』は萌々のこと頼りにしてる。下準備だけじゃなくプレイもね」
「でしょミドリン。あ、そういえば『キラ殺』のタワマンステージ行けるから今日はそこでやろーよ。マッシーが面白そうって言ってたから、頑張って解禁したんだよぉ」
「うわあ楽しみ! ありがとう萌々」
盛り上がる三人を前に、葵は我が愛しのボードゲームの話をするのが怖くなってきた。
「皆ゲームが本当に好きなんだね・・・じゃあちょっと、ウチには呼び辛いなあ」
「ん? アオイっちの家? どゆこと?」
「その・・・ウチにも来てほしいって思ってるんだけど・・・呼んでもらってばっかじゃ悪いから」
「なんだそんなことぉ」
萌々が顔の前でブンブン手を振った。
「別にいいよぉ。だってアオイっちの家、ゲーム機ないんでしょ?」
「しかも結構遠いって言ってたじゃない。べつにわざわざ葵の家に行くメリットなくない?」
「で、でもさやっぱり申し訳なくて。ウチにも来てほしいの」
食い下がる葵から必死さが伝わったのか、眞代が二人を見やった。
「ここまで言ってくれてるし・・・次は葵ちゃん家にお邪魔させてもらう? 葵ちゃん家でもゲームはできるでしょ?」
「あーMSG(持ち運びできる小型の個人用ゲーム機のことらしい)持っていくってことぉ?」
(それは・・・ちょっと)
我が家にまで来てデジタルゲームをされては困る。
「確か全部、MSGでプレイ出来たもんねぇ。まあそれならモモはありかも」
「あたしは反対」
挙手して翠が言う。
「MSGって画面小さいし、それに三つしかないから四人で出来ないじゃない」
「そこはさ翠、代わりばんこに使うとか」
「それが嫌なの。ゲームはテレビでやりたいの」
プイと横を向く翠。
「そ、そういうことなら・・・」
ここぞ、と葵は口を挟んだ。
「わ、私の家でテレビゲーム以外のことをして遊ぶっていうのはどう?」
再び三人の視線が葵に集中する。緊張のあまり、顔を赤くしてどもりながら続ける。
「ち、違うゲームしたらどうかなって。その、テレビゲームみたいなデジタルじゃないゲームがあるらしくて・・・」
「・・・」
「・・・」
「・・・」
(だ、大丈夫かな。誰か何か言ってぇー)
「その、ボードゲームっていうらしくて、実際にサイコロ振って駒を動かしたり、タイルを置いたり、カードを引いたりして遊ぶみたいで。それならウチでもでき」
「要するに、オセロ的な? うーん、モモはいいや。なんか難しそう」
萌々は葵から顔を背け、テーブルの上のクッキーをつまんだ。翠はというと、既にテレビの方を向いて画面を操作している。
「あたしもパス。テレビゲームの方がいい」
「そ、そっか」
最後に、葵は眞代の方を見た。今自分がどんな顔をしているか、不安で堪らなかった。
「わ、私もちょっと調べただけで・・・あんまり詳しくないのに勧めるのって変かもしれないけど。ま、眞代ちゃんはどうかな? やってみたい?」
「面白そうだね。でもごめんね」
少し困ったように眞代は笑った。
「私、ゲームはこの三つだけでいいかなって思ってるんだよね」
「あー・・・」
「だから、葵ちゃんがわざわざボードゲームを用意してくれなくても大丈夫だよ? お金もかかっちゃうしさ」
「そ、そっか。なら良かった・・・」
自分の声が遠くから聞こえた気がした。ボードゲームはテレビゲームとは違うものなのに、違った良さがあって面白いのに。ボードゲームはすでに沢山持っているのに。何も言葉が出てこない。
頭が熱い。喉の奥が重い。三人に言われた言葉が脳から喉にかけて熱く膨らみ、葵を内側から圧迫し続けているようだ。
「ホントにごめんね、折角調べてくれたのに。もしかして葵ちゃんはボードゲームに興味あった?」
「あ、うううん。全然大丈夫! こういうゲームがあるんだなーこれならウチでも出来るなーって思って紹介してみただけだから! どうしてもボードゲームで遊びたいわけじゃないから!」
「そっか、じゃあ良かった」
優しく微笑む眞代。葵はこくこくと首を動かすので精一杯だった。
萌々はしばらく二人のやり取りを黙って見ていたが、突然頭上でパンと手を叩いた。
「じゃ、決まりだねぇ! 誰もやりたくないからボードゲームはナシ!」
「これからも、あたしか萌々ん家でゲームすればいいじゃん。じゃあこれで決まりね。議論終了。早く続きやろう」
翠はテレビの画面を止めた。
「決めた。次は海ステージね。ここなら絶対負けないから」
「ざんねーん。モモここ、すっごい得意なんだもんね!」
「言ってなさい。てか、『Easy』で張り合うのってどうなのよ。葵がせめて『Nomal』でプレイ出来たらなー」
「ちょっと翠、葵ちゃんにプレッシャー掛けちゃダメでしょ。葵ちゃんには葵ちゃんのペースがあるんだからね」
三人の声を聞きながら、葵の目線は徐々に床へと下がっていった。
小学生の頃とは違う。恐れていたことは起こらなかった。馬鹿にされたわけでも、揶揄われたわけでもない。だから平気なはずだ。
(なのになんで、こんなに心が痛いんだろう・・・)
ーー
「そっか、皆はボードゲームに興味がないのか・・・」
葵の話を聞いた父親は、我が事のように悲し気な顔をした。母親は一言も言葉を発さず、黙々と端を口に運び続けている。
当の葵はというと、テーブルを前に俯いたまま微動だにしなかった。好物のヤンニョムチキンも、今夜はとても食べられそうにない。そのくらい、今日のことがショックだったのだ。
「まあ、ボードゲームやりたいって子は少ないか・・・」
「私、私は・・・」
重い喉の奥から何とか声を絞り出す。だが、そこから先は言葉にならなかった。
(私、皆と一緒にボードゲームしたかったなあ・・・)
ぼっち弁当になるところを救ってもらえた。お菓子交換をして、家にも呼んでもらった。教えてもらいながらテレビゲームをした。
全部全部初めてで、舞い上がるような心地だった。三人を、かけがえのない友達だと思った。だからこそ、期待してしまった。
葵の目から、熱い雫がポロリと落ちた。
「ボードゲームのことなんて、言わなきゃよかった・・・」
「それは違うよ、葵」
父親は語気を強め、首を横に振った。
「パパ以外の人とボードゲームしたいって思ったんだよね? パパはすごく嬉しいよ」
「・・・」
葵は俯いたまま返事をしなかった。何が嬉しいのだろうか。結局、あの子達とボードゲームができないというのに。
「パパ」
母親が、父親の前から空になった皿を取り上げた。
「今日は私が片付けといてあげるわ」
「いいのかい?」
「葵の相手をしてあげれば?」
「だそうだ。葵?」
顔を伏せたままこくりと頷いた。正直なところ、今はいつものボードゲームが恋しかった。父親と遊びたかった。
安心するからだ。そう、無性に安心したくて堪らなかった。
「今日は、タイルを敷き詰めたい気分・・・」
「オーケーあれね。じゃ、パパは先に準備してるからね。葵も食べれるだけ食べたらおいで」
「うん、分かった」
今晩初めて箸を手に取った。
(栄養補給しなくちゃ・・・)
ヤンニョムチキンはいつも通り、辛くて甘くて蕩けるような味わいだった。すべて平らげ、ゲームが始まった。
一時間ほど遊び、休憩中に葵は自分からこう切り出した。
「来週月曜日、あれをやりたいな」
指したのは、1プレイに三、四時間はかかる重量級ゲームだ。
「帰って宿題終わったらすぐやりたいから、夕方から予定を開けておいてほしいんだけど・・・」
「分かった。準備しておくよ。けど、いつもは月曜日って」
「えっと、その日はゲームしに行かないって断っちゃったから・・・」
今日翠の家を出る際に誘われたのだが、とてもOKする気にならず断ってしまった。「用事がある」と言っておいたのでそれ以上追及されることはなかった。
「別にいいよね、一回くらい・・・」
「そりゃ断ったっていいけど、でも葵・・・」
父親は少し心配そうに葵を見た。
「もうその子達と遊ばないなんて言わないよね? 嫌いになってなんかないよね?」
「う、うん。うん・・・」
「ちょっとパパ、今はやめなさいよ」
母親がぴしゃりと言うと、父親はバツが悪そうに口をつぐんだ。
別に嫌いになったわけじゃない・・・と思う。が、今は三人と一緒に遊ぶことをあまり考えたくないのだ。
「ね、パパ。もう一回やろ」
「うん、そうだね」
「適当なところで切り上げなさいよ。寝坊は厳禁だからねー」
レモネードー父親お手製であるーのグラスを片付け、母親は一足お先に寝室に向かった。
結局、日付が変わるまでボードゲーム三昧だった。翌日金曜日が休みだったので気の済むまで遊び、沢山の勝利で満たされてグダ寝することができた。
が、その日から二泊三日で旅行に行く予定があり、「だから言ったのに」と一人早起きした母親をきりきりさせた。
結局滑り込みで新幹線に間に合い(駆け込み乗車はしていない)、つつがなく旅行が始まった。
山の展望台から最高の景色を眺め、城下町でスイーツを食べ歩き、アトラクションの待ち時間にカードゲームをして、天然温泉から出たらボードゲームで遊んで。
旅行から帰る日曜日には、葵の心はすっかり回復していた。
「皆とボードゲームができないのは残念だけど、次に遊ぶのが楽しみ!」
三人にあげるお土産を手に、葵はご機嫌で家へと凱旋した。
そして次の日月曜日。葵は休み時間に読書をして過ごし、時折廊下の方をちらちら見た。もし眞代が来てくれたのなら、紙袋からお土産を出して見せようと思っていた。
ワクワクしながら待っていたが、ついにその日彼女は葵の教室に顔を見せなかった。そりゃそうだ。いつも通りなら、次に遊ぶのは木曜か土曜のはず。明日か明後日にならないと三人の予定もまとまらないだろう。それまでは眞代が来なくてもおかしくない。彼女だって忙しいのだ。
少しがっかりしつつも、葵はその日はそっと家に帰った。明日になれば、と期待を抱きながら。
だが火曜日になっても、水曜日になっても、眞代が葵の教室に来ることはなかった。
『この日、スイーツビュッフェ行こう!』
そう決めていた日曜日が過ぎてなお、眞代は葵の前に姿を現さなかった。そして、葵が三人と遊ぶどころか顔を合わせることもなくなったのだった。
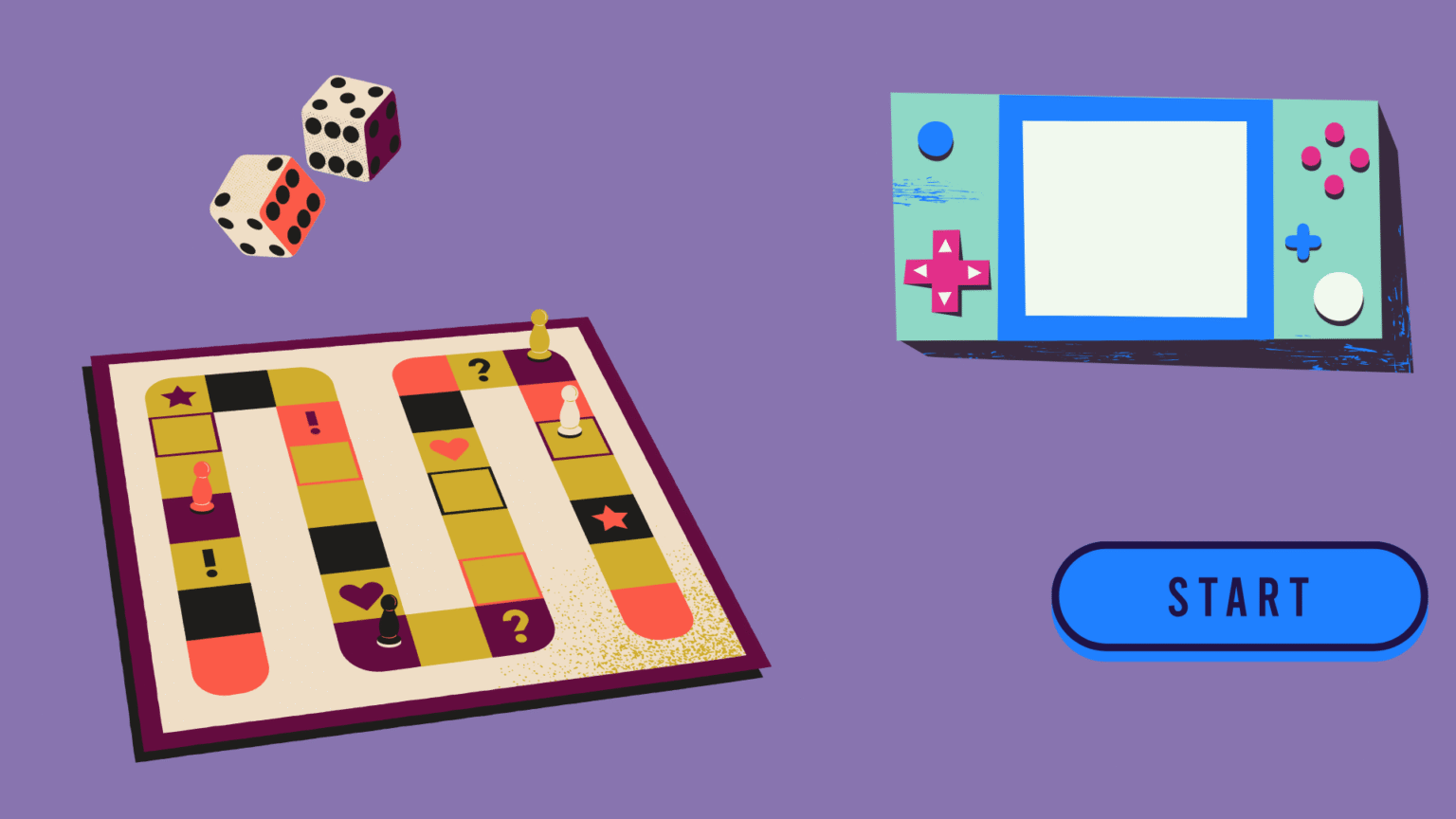

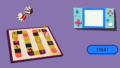
コメント