「それでは、今日からしばしお別れだ。家族に顔を見せてしっかり休めよ。解散っ!」
ヤーグ店長の言葉が終わるや否や、従業員達は我先にと制服を脱ぎ店の外に飛び出した。
国の首都を始め、様々な都市部で店舗を展開しているアーブル商会。アーブル家は交易事業を手掛ける富裕な一族であり、交易で得た品を一般市民向けに販売している。
ヤーグが店長を務めるのこの店では、今日から二か月間、従業員に休暇が与えられる。異国の商品を積んだ船が港に戻るまでの期間だ。
従業員の多くは故郷に帰ると言っていたが、他都市へ旅行に行く者もいるという。皆がわいわい騒ぎながら駅に向かうのを見送ったヤーグは、ただ一人店内に留まっている従業員を見やった。彼もまた他の従業員同様、制服のベストと蝶ネクタイを外したラフなシャツ姿で床にしゃがんでいる。
「さあ、アーブル荘園へ行くぞ」
「うぃーす」
彼は歯を見せて笑い、耳の横で蝶ネクタイをブンブン振り回した。
ーー
ヤーグは元々、アーブル家の屋敷で働いていた使用人であり、主人であるアーブル氏からの信頼を得て店舗の一つを任されている。今回の閉店期間中、アーブル家が所有する荘園の管理をするよう命じられていた。
本来は一人で向かう予定だったが、今はこうして二人で馬車に揺られている。早朝に都市部を出立して、今はもう朝七時だ。
「もうすぐ着くぞ、コーネル」
「あ、ふぁい」
若者が目を擦り擦り、んんーと伸びをする。襟元が寛げられており、寝起きだから髪もぼさぼさだ。
「出発してから三時間、ずっと爆睡してたぞ。あんまり緊張していなさそうだな」
「いや、そんなことないですって。ただもう、モーレツに眠くって眠くって」
「ふっ、俺がお前らをこき使ったから疲れたとでも言いたいか」
「ご名答、さすがヤーグさん。なーんちゃってね」
まだあどけなさの残る顔で、ケタケタと笑っている若者。従業員のコーネルは店舗で働き始めて一年目の新人だ。緑色の目に栗色の癖毛。日焼けした小麦色の顔にはそばかすが浮かんでいる。田舎出身ではないか、と思ったらやはりそうだった。
そんな彼が今回の二か月間行く当てがないと知ったのは一週間前のことである。
「お前、閉店中は日雇いで生活するつもりなんだってな」
「あ、はい。そうっすけど」
「故郷に帰らないのか? のんびりできる身分じゃないのか?」
「あーその・・・」
コーネルは少し俯き、目を逸らして答えた。
「俺、家には帰りたくないんです。その・・・色々上手く行ってなくって」
家族と何かあったのかと察したが、口には出さなかった。
「大丈夫っすよ。俺、接客も計算もばっちりです。飲食店とかを当たれば、どこかしら雇ってはくれるはずですから」
「うーん」
帰りたくないというのであれば無理に帰ることもない。だが都市に出て来たばかりの若者が、悪質な業者に引っかからずにいられるかどうか。
「まあ、ちょっと待ってろ」
ヤーグはアーブル氏に電話を掛けた。
「荘園管理に使える人材がおりまして」
従業員としての働きぶりを述べると、二つ返事で採用された。こうして、コーネルにはヤーグの補佐としての仕事が与えられたのである。
「さあ着いたぞ」
馬車は荘園の門をくぐり、しばらく進んでから止まった。馬車を下りたヤーグの目に、懐かしい風景が飛び込んできた。
◇◇
広大な丘陵地帯を覆う青々とした畑、それを横断する道、点々と建つ小屋と濃い緑の森。
「これが、アーブル荘園・・・」
「広大だろう」
「はい」
目を凝らしても畑の端が見えない。
思わず、比べものにならない、と口にしていた。やはり、都会の金持ちは田舎の引きこもりなんかとは違う。
「さあ、荷物を置きに行くぞ」
ヤーグはコーネルの肩をポンポンと叩いて歩き出した。彼が向かうのは、畑の中にポツンと一軒建つ赤いレンガ造りの家だ。
「あれが、俺達の寝泊まりする家だ。書類仕事なんかは基本あそこでやる」
「豪華ですね」
「俺達は管理人だぞ。そりゃ、荘民とは待遇が違うさ」
とその時、トウモロコシ畑からダッと何かが道に飛び出してきた。
「おっと!」
「わっ!」
コーネルが反対側に避けるのと同時に、飛び出してきた何かがあわてて急停止した。まだ十歳かそこらの腕白そうな子供だ。コーネルらの前からパッと飛びのき、腕を組んでこちらを睨み上げてくる。
「あっぶないなー。気を付けてよ」
「申し訳ございません、坊ちゃま」
白いブラウス、サスペンダー、靴。土や泥が付いていても紛れもない高級品だ。成程、アーブル家の一員に違いあるまい。
ヤーグが荷物を降ろし、帽子を取って深々と頭を下げる。とりあえずコーネルもそれに倣った。
少年は二人を睨んでいたが、ふとヤーグを見て目を丸くした。
「あれ、もしかしてヤーグ?」
「はい。二年前までお屋敷に勤めておりました、ヤーグでございます。お久しゅうございます、坊ちゃま」
「やっぱりヤーグだ! え、いつ帰って来たのさ!」
「たった今でございます」
「えー! パパに教えてあげなくちゃ! パパー!」
少年はくるりと背を向けて再びトウモロコシ畑の中に入って行く。入れ替わるように、数メートル先から恰幅の良い紳士がトウモロコシをかき分けて出て来た。
「こっちから声がしたと思ったんだが・・・おっ、ヤーグか」
「只今戻りました、旦那様」
再びヤーグが恭しく礼をする。
「この度は重大なお役目を賜り、光栄に存じます」
「そうかそうか、今日からだったな。まあ宜しくな、そっちの君もな」
と、コーネルに目を向ける。整った装い、堂々とした体躯、整えられた口髭、落ち着いた威厳のある声。
(この方が、アーブル家当主・・・)
コーネルの大本の雇い主だ。再度ぴしりと姿勢を正す。何度も撫でつけた髪に再度櫛を入れたくなる衝動に駆られつつ、口の中で五、六度練習した挨拶を口にした。
「この度はお目をかけて頂き、誠に光栄に存じます。アーブル家の為、誠心誠意尽くす所存にございます」
「そうか。ヤーグの言うことをよく聞いて励むように」
「はい」
「さて、我が息子はどこへ行ったのかな」
「坊ちゃまでしたら、先程こちらにお見えになりました」
「そうか、じゃあここで待っていたら来るかな。いやなに、ここにはケーキを食べに来たんだ。今朝摘んだばかりの果物をたっぷり入れたやつをな。待ってる間、鬼ごっこしていたんだが。あの子はどこに行ったのやら」
「パパーッ」
さっきの子供がトウモロコシ畑から飛び出し、アーブル氏の腰にぶつかる勢いで抱きついた。
「ケーキ焼けたって! お茶の準備もできたって!」
「分かったよニルン、じゃあハーブ園に行こうか」
腰には結構な衝撃だったはずだが、アーブル氏は息子を咎めることなく笑って頭を撫でてやっていた。
「楽しみだね、兄ちゃんもいればよかったのにな」
「兄ちゃんが帰ってくるのは夜だからね。そうだ、少し果物を持って帰ってゼリーを作らせようか」
「やったあ」
アーブル氏はニルン少年をひょいと持ち上げ、肩に乗せた。そのままくるりと背を向けようとして、「あ、そうだ」と向き直った。
「羊は、今度の祭りでパイに使う。子羊は殺さないで、大人の羊も指示した数だけ肉にするように」
「かしこまりました」
それだけ言うと、息子を肩車したままアーブル氏は去って行った。ケーキのことや上の息子のことを楽しそうに喋っている。ニルン少年はあんまり大声なので遠くなってもしばらく会話が聞こえてくるのだ。
(親にもこんなに差があるんだな)
小さくなっていく親子の背中を見つめながらコーネルはそう思った。
コーネルの親は肩車なんてしてくれなかったし、もし不意に腰に抱きつこうものなら間違いなく鉄拳制裁で答えられただろう。
コーネルの故郷は都市部から遠く離れた田舎にあり、実家はそこの地主だ。アーブル家ほどではないが財産は有り、農夫を何人も抱えた由緒正しい名家である。
どこで嗅ぎつけたのやら、「坊ちゃん暮らしだろ、いいな~」と従業員仲間からよく言われる。説明するのも面倒なので「まーな」と流すが、コーネルからすればそんなお気楽なものではない。
あの家ではとにかく、「由緒正しい地主の家にふさわしい人間であること」を求められた。家のしきたりに従うこと、品格を保つこと、そして目上の者には絶対服従。あの家で、コーネルは家長である父親の厳重な管理下に置かれていた。
作法と勉強、仕事が一日の大半で、上手く行かなければできるまでやり直し。遊ぶ時間はなし。さらに、何をどの器で食べるか、この日は何を着るか、この時間はどこで何をするか。起床から就寝まで、一日の生活の全てのことを父親が決めたとおりに行わねばならなかった。
コーネルは反発し何度も逆らった。好きな服を着て家を飛び出し、外で遊びまわったものだ。父親は言うことを聞かないコーネルを殴りつけ、隠し持っていた菓子や娯楽本を探し出して捨てた。
母親もそれに追従した。暴力こそ振るわなかったものの、小作人が見ている前でも構わずコーネルを大声で𠮟責した。
狭い田舎のことだ。人々に「叱られてばかりの問題跡継ぎ」の噂は浸透し、コーネルの肩身は狭くなるばかりである。だから十六の成人を迎えた日、待ってましたとばかりに彼は田舎を飛び出した。従順な弟に跡取りの座を押し付ける由を書き置いて、一人都市部にやってきたのである。そして、そこで運良くアーブル商会に雇われて今に至るというわけだ。
あの場所で過ごした時間は最悪だった。だが最早、全て過去のものだ。故郷も、あの家も、家族も。地主の跡取りとして教わったことも全て。
(俺はアーブル商会で新たな自分を始めるんだ)
改めて決意し、コーネルはヤーグについて小屋の中に入った。
ーー
見渡す限りの畑と、その中で仕事をする農夫達。進んでも進んでも、なかなか景色は変わらない。
ヤーグ曰く、畑は百を超えるらしい。そしてなんと荘園内には野生の森林が三つ、放牧用のなだらかな丘が四つ、さらに数本の川まで通っているという。
「荘民は、千はいるかな」
荘民とは、荘園に住み込みで畑を耕す者、家畜の世話をする者、その他雑用をする者等、管理者の下で労働に勤しむものを指す。
「すごい規模ー。そりゃ確かに、管理者が一人じゃ足りないなあ」
荘園は、ヤーグを始めとする十数人の管理者で分担して取り仕切ることになっている。
「俺たちの持ち場はここ、南東区だ。で、今日の予定だが」
ヤーグは胸ポケットのメモを取り出した。
「午前中は畑仕事を巡視。それから麦畑を確認して生産高見積もり。午後は野菜の収穫があるから、それと貯蔵管理の指揮。収穫量から、商品用、屋敷用、荘園用の量を決定して出荷準備。夕方になれば羊飼いが戻ってくるから、羊達の様子を報告させなきゃいけないな。そんで、旦那様宛の報告書作成、屋敷から来た使用人に渡す。最後に諸々の戸締りを確認して終わりだ」
「俺は、ヤーグさんについていればいいんすよね」
「そう。俺が指示したことをやってくれればいい。まあ助手というわけだな。主な役目は俺の書記だ。お前、店でも綺麗な字を書いてたもんな」
「へへっ、そんなふうに思ってくれてたんっすね」
「まあな。今日は速記が多いと思うが、頑張って読みやすい字で書いてくれよな」
というわけで多忙な一日の始まりである。コーネルは休みなく手足を動かしていた。ヤーグの後をついて広大な荘園を巡り歩き、ヤーグが交わした会話という会話、計画、情報、計算をひたすらに記しまくった。
ヤーグが書類仕事で手が離せない間は、コーネルが赤レンガの家を出てヤーグの伝言を伝えるなど使い走りに徹した。一人で荘民と接する時間は決して居心地のいいものではなかったが・・・まあヤーグの代理人としての役目を果たすだけだと割り切った。
最後の一つ、羊小屋の戸締りを確認したのは夜の八時前だった。外はすっかり暗く畑には人っ子一人いない。
「ああ、やっと終わった」
赤レンガの家に戻れば夕食が待っている。コーネルは一目散に駆けだそうとしたが、ヤーグに止められた。
「俺は走れん。頼むからゆっくり歩いてくれ」
「あ、はいはーい」
「いや、ちょっとだけ座らせてくれ」
どっこいしょ、と切り株に腰を下ろす。久々のフィールドワークが体に堪えたのだろうか。ヤーグの声には疲労が滲み、足も棒になったようだった。
「ヤーグさんお疲れ様です」
近づいて声を掛けてくるものがあった。帽子を被った少年だ。荘民の中で、今日最後にヤーグと話していた羊飼いである。ヤーグは座ったまま手を挙げて応える。
「ああ、ご苦労だったな」
「お疲れさまでした。ゆっくり休んでくださいね、羊飼いさん」
「じゃまた明日、ヤーグさん」
羊飼いの少年はコーネルの方には見向きもせず去って行った。否、去り際に一瞬睨まれた。
彼は、羊小屋の近くにある宿舎ー所々に建っていた木の小屋は、荘民用の宿舎だったらしいーではなく畑の向こう側へと走って行く。
その先、少し遠くに明かりが見えた。赤々と燃え盛っていて、よく見たら煙が上がっている。
「焚火?」
「ああ、南東区の荘民は皆あそこにいる。区画別に広場があってな、夜は荘民がそこに集まって食事をとるんだ」
「そうなんすね」
区画ごとの荘民・・・つまり何十人が一堂に会するということか。うるさいし暑苦しいことこの上ない。
自分達は室内の静かな環境で食事がとれる。幸いなことだとコーネルは思った。
赤レンガの家に戻り、手を洗って食堂に行くと嬉しい光景が待ち構えていた。
テーブルに並ぶ、スイカくらいの大きさの二つのバスケット。覆いきれをめくってみると、片方にはミートローフとキッシュ、もう片方にはライ麦パンの塊と瓶が一本入っている。瓶のふたを開けると、野菜のポタージュが首までつまっていた。
「うおう、うまそー」
棚から食器を出して二人でテーブルに座れば待ちに待った食事の始まりだ。
一口目を食べたところでコーネルは思わず目を見開いていた。
「どうだ、美味いか」
コクコクと首だけ動かす。
「そうだろ、屋敷のシェフが作った飯だからな」
「?!」
「管理人には、屋敷の使用人と同じ食事が三食きっちり出されるのさ。今日の朝昼は都市部で買ったもので済ませたが、明日からは毎食シェフの賄いが食べられるぞ」
(こういうのが毎食かー)
店の従業員用の食事より贅沢なメニューで品数が一つ多い。さらに、食材が良いし味付けも凝っていて美味しい。嬉しい、と思う反面少し残念でもあった。
(量がな・・・)
本当は、自分一人でバスケット二つともペロリと平らげられてしまう。店にいたころはもっと簡易な食事だったが、お代わりは自由だった。
(あと、冷めてる)
これが、残念ポイントその二。このポタージュスープなどは特に、瓶に入れたばかりの頃はホカホカだったろうと残念でならない。数百メートル離れた屋敷で作って運ばれ、夕食の時間を待って食べるので仕方ないと言えばそうなのだが。
「満足だろう? 流石は旦那様」
「そっすね」
「今日は助かった。しっかり食べて明日からも宜しく頼むな」
「任しといてくださいよ」
ウインクしながら、ヤーグの前では本音を言わないのが無難だとコーネルは思った。
「ところでヤーグさん」
「なんだ」
「祭りって何のことです?」
ああ、とヤーグは匙を置いた。
「毎年この時期になると行われる祭りがあるんだよ。お屋敷では客人を招いてご馳走を振舞ったり狩りなんかの娯楽を楽しんだりするんだ」
「ふんふん」
「その日は荘園の仕事も一日休みでな。荘民は荘民で、ここでご馳走を食べて一日騒ぐのさ。当然この日は酒も無制限に飲んでいい」
「ほうほう」
「あと、お屋敷と荘園で、何かしらの共通のメインディッシュが出されるんだが、それが今年の場合は羊のパイなのさ」
「毎年変わるんすか」
「ああ、去年は鹿肉のローストだな。荘園内に森があるだろ。あそこに野生の鹿が生息しているから、当日に仕留めて捌いて料理してと少々慌慌ただしかったらしい」
「ああ、なーるほど」
「その点でいえば今年は余裕がある。だがその分、羊の飼育には注意しなきゃならん」
ヤーグはうんうんと頷いていた。
ーー
次の日の仕事は、広場に南東区の荘民を集めて週に一度の朝礼をするところから始まった。今日は朝からカンカンと日が照っており、誰もが顔を真っ赤にしてダラダラと汗をかいていた。
全員が集まったのを確認すると、ヤーグが全体的な指示や注意事項を書いた紙を手渡してきた。
「お前が読み上げるんだ」
「俺が?」
「よく通るいい声をしているだろ」
「そーゆーことなら」
紙を受け取り、大声で読み始める。これではまるで、自分が管理人にでもなったかのようだとコーネルは思った。
紙の横からちら、と目の前の群衆を見ると、皆黙って話を聞いているものの、無表情や険しい顔の者が目立つ。
(難しく考えんなよ。俺は管理人じゃない。管理人の補佐だ。ヤーグさんの手足となって働いてるだけさ)
急に来た十代のガキが管理人側になって自分たちに指示を出すのが面白くないのだろう。とはいえ、正真正銘の管理人ヤーグの前だ。勝手に立ち去ったり文句を言ったりする者はいない。コーネルは敵意を知らんぷりして紙面の内容を最後まで読み上げた。
読み終わった時、流れ出る汗をようやくタオルで拭うことができた。
「では解散だ。各自仕事に励むように」
ヤーグの締めの挨拶で荘民らはワッと広場の水汲み場に駆け寄って行く。一人ひとりが小さな水筒に水を入れるのを見てコーネルはぽつりと呟いた。
「あれで足りるんかな」
「畑の近くにも井戸がある。大丈夫だろう」
コーネルの呟きを拾ったヤーグは、既に今日の予定を書いたメモに目を落としていた。
「さて、今日はまず野菜の酢漬け作りの監督からだ」
「はい、了解っす」
ヤーグの後に続こうとした時、ふとコーネルは足を止めた。小さな水筒をぶら下げて羊小屋に向かう、ゆうべの羊飼いの姿が目に入ったのだ。確か、牧草地のある丘の上に水を確保できる場所はなかったはずだ。
ヤーグに断り、コーネルは早歩きで羊飼いに近づいた。
「ちょっといいですか!」
声を掛けると、彼はピタリと足を止めた。まだ若く、コーネルより一つか二つぐらい年上の少年だ。コーネルより背が高く褐色の肌をしている。目が細く、傍から見てちょっと目つきが悪い。今はこちらを睨んでいるので人相が悪いといった方が良いか。
「何」
「これ、どうぞ」
コーネルは自分の水筒を差し出した。羊飼いは受け取らず、怪訝そうな顔をする。
「どういうこと」
「俺の水、持って行ってください。今日は暑いですから」
「それ、ヤーグさんの指示?」
「いいえ、俺の独断です」
「あっそ」
羊飼いはそっぽを向き、コーネルに構わず羊小屋を開けようとする。
「あの!」
「うるせえ、いらねえよ。てか何、運よく管理人になれたから、調子に乗って口出ししてみたくなったわけ? お生憎様、お前なんかと話すことは何もねえよ」
(俺だって別に、お前なんかと話したくねーよ)
内心イライラしながらも羊飼いに追い縋る。
「今日はめちゃくちゃ暑い日です。昨日とは比べものにならない。水は少しでも多めに持って行かなきゃ危ない。俺は水分補給はわりといつでもできます。でも、あなたは一日中丘の上にいるのでは?」
羊飼いが戸を開ける。中からドッと羊の群れが出てきてコーネルは慌てて後ずさった。
「これくらいの暑さ、別に平気だ。俺は何年もここで羊の世話をしてんだぞ。来たばっかのよそ者がなにを知ったかぶってんだ」
言い捨て、羊を引き連れて丘のほうへと行ってしまった。
「ちぇっ、なんだい。人が折角心配してるのに」
コーネルは振り返り振り返り、自分を呼ぶヤーグの元へと戻ったのだった。
ーー
野菜を切って樽に入れ、酢を流し入れる。樽六十個分になった。これは例年の四十個分を遥かに上回っている。例年、屋敷7、荘園3の割合で振り分けているが、そのことでヤーグが頭を悩ませていた。
「樽四十個・・・お屋敷に入るか? 倉庫に受け入れ可能か、前もって聞いておくんだったな。他の料理に回せって言われてたかもしれないのに」
「大丈夫っすよ。使い走りに出た際に、電話が掛かってきましてね。その時に聞いときました。樽三十個でいいって。で、残りは荘園で消費しろって。すいません勝手に」
「いやいいよ、俺も忙しかったしな。むしろ助かってる。じゃあ味付けに入るか」
「あ、それなんですけどシェフが来るまで待ってもらえます?」
「?」
「心なしか傷んでいるものが多いように見えたんで、そのことも伝えたんですよ。そしたらシェフが直々に味付けを教えに来るって言うんです」
「いつだ」
「一時間くらい後です。それまでにここに書いてあるものを揃えておいてほしいって。ヤーグさん、荘民の人らに声を掛けてもらってもいいですか」
「いいよ。てかそれもやってくれれば良かったのに」
「そこは、ヤーグさんが頼りなんすよ」
そうして無事に野菜の酢漬け作りが完了した。ヤーグは水をごくごく飲み、うんうんと頷いた。
「流石、コーネルは役に立つなあ。連れてきて大正解だったぜ」
(その通り、俺は呑み込みが早くて気が利くのさ)
「なんのなんの、ヤーグさんの従業員教育の賜物ですよ」
コーネルもコップの水を飲み、窓の外を見た。太陽が高く上り、ギラギラと照りつけてくる。最悪の猛暑だ。
「さてと、畑を巡視する番だな」
「それなんですけど、たまには牧草地も見てみません?」
「あーそうだな。午前中の仕事の様子を見ておくか」
ヤーグと共に小高い丘の上の牧草地に向かう。羊がメーメー鳴きながら草を食んでいるが、羊飼いの姿はない。手分けして探し回る。
(さすがに我慢できなくて水を飲みに降りたか? 或いは・・・)
「いた」
丘の上の木からヤーグが手を振る。
「こいつ、寝てやがるぞ」
これは、予感的中ということだろうか。駆け寄ると、羊飼いはあおむけに倒れ、ピクリとも動かないではないか。顔は赤く、汗だくになっている。
「暑いからって仕事をさぼって寝るとはいい度胸だな」
揺さぶって起こそうとするヤーグを制止する。
「ダメダメダメ。暑さで意識を失っているんすよ」
「ああ、あれか? 熱中症とかいうやつ? よく知ってんな」
都会ではそう呼ばれているのか。田舎ではそんな言葉などなかった。否、暑さで体が不調になることすら認識されていなかった。
ただ、コーネルは何度かなったことがあるので警戒していただけだ。
コーネルは上を仰ぎ見た。日陰とはいえ、木の枝の隙間から日差しが容赦なく降り注いでくる。
「涼しいところに移して、休ませなきゃいけないな」
「おい、ちょっと待て」
木陰から出たヤーグの顔がこわばった。
「羊が三匹足りないぞ。どこに行ったんだ」
「え?」
丘中に散らばった羊を目で追う。確かに、朝見た時よりも減っているかもしれない。
「アッ・・・」
丘の周りを囲う木の柵の一部が壊れている。今まさに、一匹の羊が乗り越えようとしているではないか。
二人は慌てて羊を回収し、てこずりながらも全て羊小屋に戻した。羊飼いも、コーネルが担いで宿舎に寝かせた。二人とも、終始早口で動作も忙しなかった。
羊小屋の鍵を掛け、ヤーグとコーネルは無言で視線を交わしあった。先に口を開いたのはコーネルだった。
「羊が逃げたんだ。俺探してきます」
「俺も行く」
今ヤーグは、祭りのことで頭がいっぱいに違いない。
「いや、ヤーグさんは巡視を続けないと」
「そうか、そうだな。畑のことも疎かにできない・・・」
「そうそう。こういう時のために俺がいるんですから」
コーネルは一人、畑から畑へと羊を探して回った。
「羊が三頭逃げ出しました! 見かけたら教えてください!」
道すがら荘民に聞いて回るが、ほとんどの荘民には黙殺された。「頼りない補佐が付いたせいだ」と聞こえよがしに言うものもいた。
暑い。汗が止まらない。水を飲み飲み、ひたすらに探し回る。
「くそ、どこに行ったんだよ」
「多分ここら辺にはいないぞ」
背後で声がした。振り向くと、そこには羊飼いがいるではないか。
「体調はもういいんですね?」
「ついて来い」
先導する羊飼い。
「クローバー畑に一匹、ハーブ園に一匹いるはずだ。・・・最後の一匹は、川べりで草を食ってるんじゃないかな」
実際その通りだった。羊を三匹とも回収し、羊飼いが追い立てていく。
「よく分かりますね」
コーネルは、穀物や野菜の畑ばかり探し回っていた。そんなところにいるなんて見当もつかない。
「あいつらの好物のことだからな」
(一匹一匹よく見てるんだな)
妙なところで感心したが、口には出さなかった。無駄なお喋りや馴れ合いにメリットはない。
その後は会話らしい会話も生まれず、しばらく無言の時間が続くと思われたが、突然羊飼いが口を開いた。
「俺、クビになんのかな・・・」
「それは、ヤーグさんと旦那様次第ですね」
とは言え、結果的に羊が無事で熱中症のこともある。そこまでには至るまいとコーネルは踏んでいた。
「だよな、柵が壊れてること、黙ってたもんな・・・」
「は?」
思わず耳を疑った。
足を止め、羊飼いの顔を仰ぎ見る。彼は、しまった、というように口を閉じた。
「あの柵、前から壊れてたんですか? それを今まで言わなかったんですか?」
「や、その・・・」
羊飼いが目を逸らす。コーネルは最後に捕まえた羊を見た。
「もしかしてこいつ、以前にも逃げ出して川の近くで草を食べていたんですか?」
「そ、そうだ。でもその度、俺がこうして捕まえて・・・」
「馬鹿野郎」
思わず怒鳴っていた。羊飼いがびくっと肩を揺らす。
「あんた、自分が何言ってるか分かってんのか」
「あ・・・う」
「柵が壊れたのはいつだ、言ってみろ」
「に、二か月前」
「そのことはヤーグさんの前任にも伝えてなかったのかよ」
「う、うん」
はあ、とため息が漏れた。そのことを知っていたのなら、前任は到底休暇などに行けなかったに違いない。
「つい、忙しくて言いそびれて・・・」
「一言で済む話だろうが」
「や、その・・・ホントは、『お前が直せ』って言われるのかなって思っちゃって・・・」
「はあ?」
羊飼いはこれまでの横柄な態度とは打って変わって、おどおどと視線を彷徨わせている。
「俺、ぶきっちょだからどうしよって・・・それに」
「もういいです」
言い訳など聞く気はない。
(ったくよ・・・)
言うべき言葉が頭にすらすら浮かんでくる。最早、怒りを通り越して落ち着きを取り戻してしまったらしい。
「多分、あの柵をあなたに直せとは誰も言いません。二日も三日もかかるでしょうから。羊飼いはあなた一人なのに、そんなことに従事させるわけにはいかないんですよ。きっと、ヤーグさんが修理人を手配するはずです」
「そ、そっか」
「それとね、そういう大事なことは絶対に管理人に伝えなさいよ。この羊たちは、旦那様の財産です。それをお預かりしてるんです。何かあったらどうするんですか」
「うん・・・」
「厳守するべきことですよ。祭りが近いの知ってるでしょ」
「はい・・・」
「水も、明日からはバケツにでも汲んで大量に持って行きなさいよ」
「はい・・・」
終始、羊飼いは殊勝気な態度だった。もうこんなことは起こらないだろう。そうであってほしい。
その後、羊飼いとは別れた。
しばらくしてコーネルは、赤レンガの家からすごすご出ていく羊飼いの姿を目撃した。泣いてはいなかったので、多分減給処分で済んだのだろう。
ーー
こうして数日が過ぎていった。コーネルの周りで特に変わったことは起こらず、毎日が平穏だった。
そんなある日の夕方、コーネルはウサギ小屋の近くでアーブル親子を見かけた。
「本気かい、ニルン」
「うんパパ、僕この子を飼いたい」
ニルン少年は一羽のウサギを抱きかかえていた。
「今晩のために太らせておいたんだけどな」
「でもこの子、とってもかわいいよ! 家族にしたい!」
ニルン少年はウサギを抱く腕に力を込めて言った。アーブル氏は息子に目線を合わせて屈む。
「ちゃんと自分でお世話できる?」
「うん、毎日お世話する!」
「嘘じゃないね?」
「うん!」
「分かった、約束だよ」
アーブル氏は息子に手を差し出し、固い握手を交わした。
「おいお前、何覗き見してんだ」
後ろからヤーグに声を掛けられた。と、同時にアーブル親子がこちらに気づいた。
「おお、ヤーグか」
「いらっしゃいませ、旦那様」
二人して礼をする。
「ちょうどいいところに来たな」
「あのね、ヤーグ、あのね」
ニルン少年が近寄ってくる。ヤーグがコーネルに顎をしゃくった。席を外せ、ということらしい。
それに従い、その場を離れる。手持ち無沙汰なので巡視でもすることにした。
(羊はどんな感じかな?)
祭りのこともあるし、最初は牧草地からだ。丘に足を踏み入れた時、怒鳴り声が聞こえてきた。
「てめえ、俺の言うことが聞けねえってのか!」
知らない声だ。慌てて丘を駆け上がる。遠くに、二つの人影が見えた。羊飼いと、誰かだ。背中しか見えないが、自分より高身長の羊飼いの胸ぐらを掴んでいるのが分かる。
「羊の一匹くらい寄越せよ!」
(不届きな荘民か? それともまさか野盗?)
だが近づくにつれ、どちらも違うらしいことが分かった。恫喝している男が着ているのは質の良い背広で、全体的に身なりが整っている。
(声が若いな。もしかすると)
羊飼いの方を見る。自分より小さい男におどおどするばかりで、何も言葉が出てこないようだ。
不意に、彼の目がコーネルを捉えた。わずかな安堵が浮かび、必死の面持ちで叫んでくる。
「た、助けてっ!」
「ああ?」
男が振り向いた。まだ若く、羊飼いと同じ年頃の少年だった。色の白い肌に、きつい吊り目をしている。コーネルのほうを見ても舌打ちするだけで、羊飼いの胸ぐらを掴む手を離さなかった。
「どうかなさいましたか」
「こいつに、子羊寄越せって言ってるんだよ。なのに言うこと聞かなくてさ」
シャツの胸元を引っ張られるまま、羊飼いが地面に膝を打ちつけた。う、とうめき声が聞こえた。
「嫌だって言いやがるんだよ、羊飼いの分際でさ」
「だ、だって、それは、だん・・・」
「うるせえ!」
少年が羊飼いの言葉を遮る。びくり、と羊飼いは口をつぐんだ。
「いいから寄越せよ、若旦那のご命令だぞ」
思った通りだ。身なりの良さ、強気な態度、おびえる羊飼い。すべてが裏付けている。なにより、顔がアーブル氏やニルン少年に似ている。
アーブル家の長男は、羊飼いの髪を掴んで引っ張り足を後ろに振り上げた。
「おら、寄越せよさっさと!」
「若旦那様!」
腹を蹴ろうとするのを制止する。
「なんだお前」
「管理人補佐のコーネルと申します。差し出がましいことですが、旦那様がこの羊達を二週間後の祭りで振舞われるのです」
「そんなもん知ってるよ」
「今よりもその時が、羊の食べ頃かと存じます」
「だから何だよ。俺は今欲しいんだって」
「羊以外でしたらご用意できるかと」
「子羊ったら子羊だ。ちったあ融通利かせろ?」
穏便に聞き入れてもらおうと思って考えた説得はあえなく足蹴にされた。
「家にダチ共が来てんだよ。一気に五匹も出しゃあ、豪華な晩飯になるだろ!」
(一匹じゃないじゃんかよ)
「見せつけたいのよ、アーブル家の財力をさ!」
「恐縮ですが若旦那様」
コーネルはやや口調を固くした。
「旦那様のご命令により、羊はお渡しできません」
「ああ?!」
長男は羊飼いから手を放し、コーネルの胸ぐらを掴んだ。
「俺は若旦那だぞ! 命令に従えよ!」
「申し訳ございませんが、旦那様から仰せつかったことでございますので」
コーネルは怯まなかった。たとえ殴られても頷くつもりはなかった。
権威主義に屈するのが嫌だったからではない。自分の雇い主であるアーブル氏の意向に逆らうことなどしたくなかったからだ。
(雇ってもらってるんだ。誠心誠意努めるのが筋ってもんだ)
「ちっ、そうかよ」
長男は手を離した。憎々しげにコーネルを睨みつけてくる。
「おぼえてろよ、てめーら」
それだけ言い捨てて去って行った。
「どう、するんだよ。これから」
羊飼いが地面に尻もちをついたまま、ぽつりと言った。その目は去っていくドラ息子に釘付けだった。
「若旦那様を敵に回しちまった」
「どうもこうも、ヤーグさんに報告するしかないでしょ」
それで事が解決するとは思えない。だが、今後の対応をご教授願わねばどうにもならないはずだ。
「ヤーグさんを探しに行きます」
「あ、待って。俺も行く。もう帰る時刻だから」
一人でいたくないのだろう。羊飼いはコーネルの後ろにぴったりついて来た。
荘園のどこにもヤーグの姿はなかった。これは、赤レンガの家の中で執務中ということだ。
「ヤーグさん、ちょっとお話が」
玄関から呼びかけても返事はない。執務室の椅子も空のままだ。
「どこにいるんだよ」
「トイレかな? 待っていれば来・・・!」
何気なく机の上に目を落としてギョッとした。手紙が置いてある。信じがたい、信じたくない文面が並んでいるではないか。
『コーネルへ
急で悪いが、今日からニール坊ちゃまの別荘行にお供することとなった。俺が戻るまではお前が代理の管理人をやってくれ。それと、坊ちゃま次第だが、多分祭りの日までに戻れないと思う。
だがまあ、お前なら大丈夫だろう。頑張ってくれ。
ヤーグ』
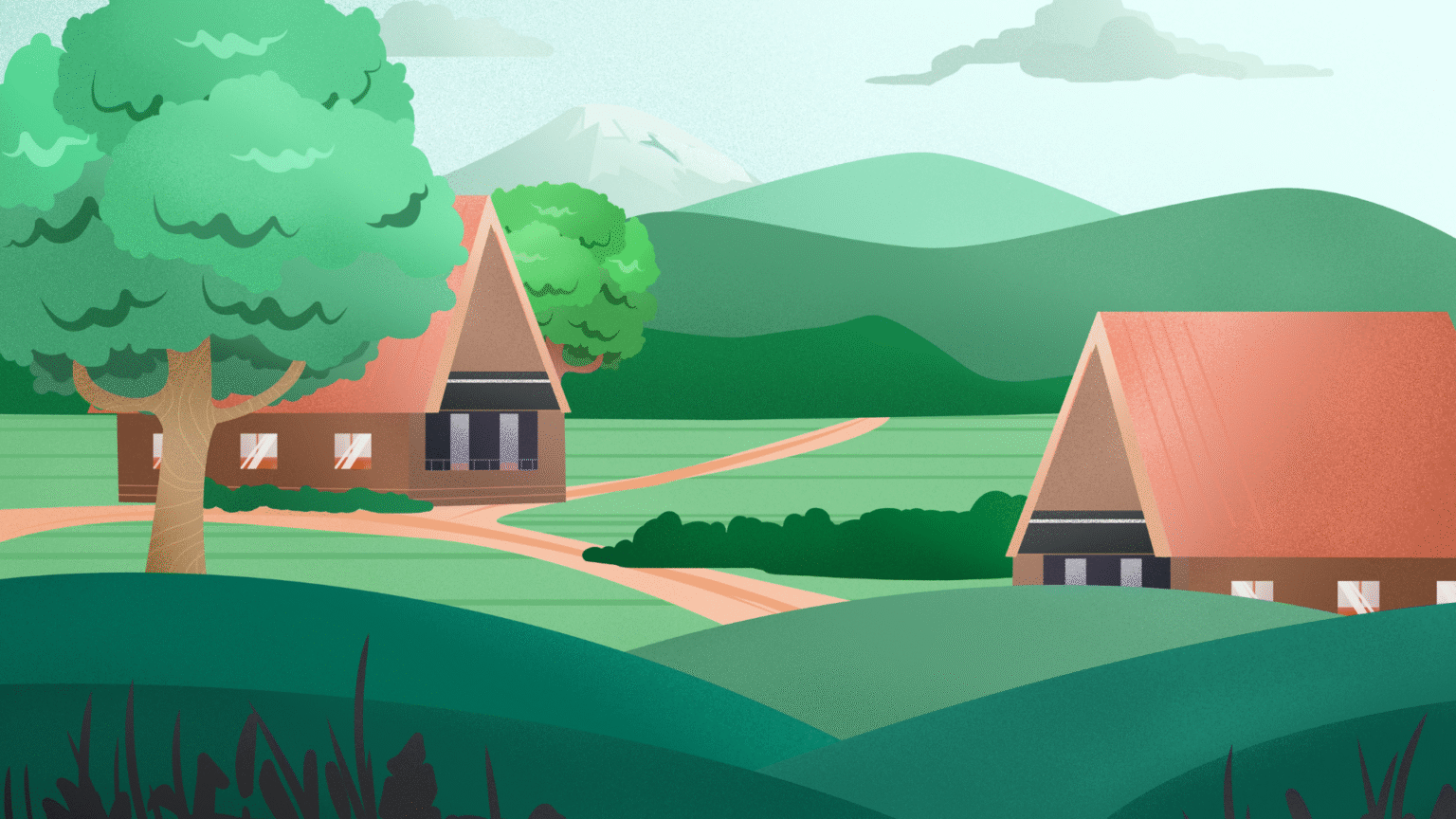
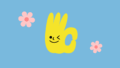
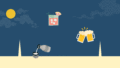
コメント