二週間後は、一大イベント「凧揚げ大会」だ。小学五年生は、図工の時間に作った凧を学校近くの運動公園で飛ばす。ただ自由に凧を揚げるのを楽しむだけでなく、クラス・個人それぞれで高度や滞空時間を競うプログラムも用意されており、かなり気合の入った大会だ。
今日は、作った凧が飛ぶかどうかを運動場で確かめる、いわゆる練習日である。生徒は、めいめいの手作り凧を空に飛ばしていく。ジャングルジムと同じ高さまでしか上がらない生徒、風に吹かれてあらぬ方向にくねる凧に翻弄される生徒。運動場ははしゃぐ生徒たちの声で大いに盛り上がっていた。
「あ、上手い。上手いね上野君」
虎の描かれた凧がひときわ高く高度を保ち続けている。飛ばしているのは涼やかな顔立ちの少年で、風が強くなっても何のその、クールにタコ糸を操り高度を保ち続けている。
「さすが上野君。本番も絶対優勝だね」
「どうやったらそんな高く飛ばせるの?」
「教えてよあつしくーん」
「いいよー。みんなで一緒にやろっか」
近くにいた女子が皆上野に群がる。当の本人もまんざらでもない様子で凧揚げのやり方をレクチャーし始めた。周りの男子達はその様子を、羨望と感服を込めた目で眺めている。
そんなふうに運動場で最も華やぐ一群を、運動場の反対側から一人の少年が睨んでいた。
メガネをかけた色白の小柄な少年である。皆から離れたところで、一人ぼっちの凧揚げをしていた。いや、揚げていなかった。タコ糸を引っ張って、ずるずると凧を地面に引きずっている。『武村直人』以外何も描かれていない凧は下着に間違えるほど真っ白で、それが右、左と、片側ずつ躓きながら前に進むさまは笑いを誘うほど滑稽だった。
実際、既に凧を揚げるのもやめて遠巻きに彼を見ている生徒達がいた。指さして馬鹿にしたり、クスクス笑ったり。一人、また一人と見物客は増え、そしてついには「下手くそー」と本人に向かって叫ぶものまで現れた。
「もういい、やめる!!」
「下手くそー」の次の瞬間には、武村少年は運動場に響き渡るぐらいの大声を上げていた。
「凧揚げなんてくだらへん! ちっともおもろない!!」
運動場中が、しん、と静まり返る。少年の叫びは止まらなかった。
「こんなので盛り上がってるお前ら、マジでアホ! 俺より勉強できへんから当たり前やけどな!!」
そして彼は、ざわつく運動場を後に走り去っていった。数名の教員が慌てて後を追い、残りがその場の収拾に取り掛かる。だが、もう運動場は先ほどまでのように盛り上がることはなかった。運動場全体にざわめきが広がり、馬鹿にしていた生徒は聞こえよがしに大声で彼の悪口を言い合っていた。
「なにあいつ」
「すねてんだろ、下手だから」
「本当のことを言っただけなのにな!」
悪口は先生達によってほどなくかき消され、運動場の反対側に届くことはなかった。上野篤志は状況を把握しきれないまま、武村少年が去って行った跡を心配そうに眺めていた。
ーー
その日の放課後、篤志は武村直人の家を訪れていた。彼は運動場を飛び出してすぐ家に帰ってしまったので、ランドセルその他もろもろを届けに来たのである。
インターホンを鳴らすと、彼の母親が出てきた。
「武村君いますか?」
「それが、帰ってきてからずっと部屋に引きこもってるの」
「じゃあ僕、彼の部屋に行ってみます」
「え、ええ、構わないけど」
了承の言葉が出るより早く、篤志は玄関に上がり込み二階へと続く階段を上がっていった。
ドアを開くと、机に座ってうなだれている武村直人がいた。直人は篤志に気が付くと一瞬ギョッとしたが、すぐに顔をプイとそむけた。
「何の用、上野」
「ランドセル、届けに来たよ」
「あっそ。そこ置いて、さっさと出てって。今勉強中やから」
直人は取ってつけたように教科書を開く。篤志はずかずかと室内に足を踏み入れ、その教科書を奪った。
「武村君。なんで急に帰ったの?」
「・・・凧揚げなんてつまらへんから」
「そんなことないよ、楽しいよ」
「そりゃ、お前は揚げれるもんな!!」
言ってから、彼はしまったというように口を押えた。
「もしかして揚げれなかったの? それで悔しいから帰ったの?」
「うっさい、違うわ! 俺はアホのお前らと違ってあんなもんに興味ないだけやから!!」
彼は篤志から目を背け、ぶつぶつと呟いた。
「何がおもろいねん、あんなん・・・」
「揚げたら分かるよ。あっそうだ!」
いいこと思いついた、とばかりに篤志は両手をパンと叩いた。
「武村君、俺が教えるから今から一緒に凧揚げしよう!」
「は?!」
「俺の家、凧あるからさ。凧揚げ大会まで練習できるよ!」
「いや、勝手に話進めんな」
直人は目を吊り上げ、篤志を睨みつけた。
「絶対嫌やぞ。大体俺、凧揚げ大会の日休むからな」
「えーなんでよ」
「どうせまた、皆で俺をバカにするんやろ」
彼は何かに耐えるようにグッと口を引き結んだ。その言葉と様子で、篤志は今日の騒動の発端が何であったかを悟った。
「下手やって笑うんやろ」
「そんなことさせないよ!」
篤志は直人の肩を掴む。
「気づかなくてごめん。もしまたそんなこと言うやつがいたら、俺がその場で謝らせるから。だけどさ、練習して凧を揚げれるようになったら誰も武村君のこと笑わないはず。いや、逆にびっくりするはずだよ」
直人は数秒間瞬きし、篤志から目を背けた。
「でも俺、お前らなんかと凧揚げしたくないし、・・・お前らだって嫌やろ」
「そんなことない!」
篤志はぶんぶんと首を振った。
「俺、武村君に凧揚げ大会出てほしい。全員で一緒に揚げるほうが楽しいに決まってる! そうでしょ?!」
「それは知らんわ」
殊勝な様子はどこへやら、直人の口調は冷めたものに切り替わる。
「それはお前のカチカンやろ。俺に押し付けんな。皆で揚げるのが楽しいかどうかは知らんわ。俺正月も、一人だけ凧揚げ見る専やしな」
「う~んそっか・・・」
「でもお前がしつこいからしゃーない。練習、付き合ったるわ」
「本当?! じゃあさっそく僕の家に行こう」
直人が準備を整えるのを待って、篤志は彼を自分の家まで連れて行った。
直人の家は街の外れにあり学校からかなり離れているが、篤志の家はさらに遠く、山を越えた先の別の町にある。
山を下りたところの道路の両脇には、無限に続きそうな田畑が広がっていた。道路を進んだ先には小さくまとまった住宅街があり、その周りでは原っぱや花畑、良く茂った並木道が幅を利かせている。自然豊かな地域で人口密度が低く、商業施設もほぼない。
「ド田舎ー」
「練習し放題の場所だよ」
篤志は直人を家のすぐそばにある原っぱに連れて行った。広々としていて人っ子一人いない。凧揚げの練習にはもってこいの場所というわけだ。
篤志が家から持って出た凧(篤志の兄が小学生の時に揚げたもの)を広げれば、いよいよ練習開始だ。
「風向き逆逆!」
「強く引っ張りすぎだよ!」
すぐに「凧揚げ」ができるわけではない。直人はいちいち口答えしたし、何度も木に凧が引っかかってその度に篤志が登って凧を取らなければならなかった。
一度、篤志は木から降りる際に腕を枝で引っ搔き出血してしまった。
「ひー」
「そこまで俺に凧揚げ大会出てほしいん?」
腕の傷を舐める篤志を見て、直人はぽつりとつぶやいた。
「そりゃ、俺みんなで遊ぶの好きだもん。それに」
篤志は空を見上げ、遠い記憶を思い出しながら続けた。
「大勢で遊んでる時に、誰か一人だけ仲間外れになるの嫌なんだ。僕も昔、辛い思いしたからさ」
篤志の住む町の人口は少なく、同い年はほぼいなかった。父親の弟一家が近所に住んでおり、昔はよく遊びに行ったり来たりというのが日常茶飯事だった。だが従兄弟達は、篤志よりも篤志の兄達とばかり遊んでいた。
理由は単純。行き来が盛んだった当時、篤志は三~五歳で、従兄弟や兄達は小学校中高学年だったからだ。十代を迎えるころなど、とにかく自分の好きな遊びに熱中するもの。幼い篤志のペースに合わせてあげるとか、篤志でもできる遊びに付き合ってあげるとかとてもそんな気にはならない。というわけで、付いていけない篤志を放って自分達の好きな遊びをするのが定番となっていたのである。
それでも最初の頃は一緒に遊んでいた。ゲームに入れてもらったり、ドッジボールや凧揚げに参加したりした。だが篤志は、ゲームのルールがちんぷんかんぷんで、ドッジボールは手加減がいるし、凧は何度も踏むし木に引っ掛ける。合わせてあげることにイライラが募った従兄弟の一人が、「篤志君には難しいから」とついに断り文句を口に出すようになった。それで、篤志はもう遊びの輪に入らなくなった。
拒絶された理由も分からず、とても悲しい思いをした。従兄弟から解放された兄達がその都度構い倒してくれなければ、心の傷はもっと大きいものになっていただろう。
「俺仲間外れにされてすごく嫌だった。寂しかった。だから、武村君も自分から一人ぼっちになってほしくない。皆と一緒に凧揚げしてほしい」
「・・・」
「結構時間たったね。そろそろ帰る?」
夕方になったので篤志は直人を家まで送っていった。篤志が過去の話をしてから直人は一言も口をきかず、黙りこくって篤志の横を歩いていた。
だが家に着いて門を開ける時、不意に彼は篤志の方を振り向いてこう言った。
「勘違いすんなよ、俺は一人でいるのが好きなんやからな。仲間外れでも平気やぞ。お前みたいな、お前みたいな・・・可哀そうな奴とは違うんやからな!!」
べえっと舌を出し、ドスドスと音を立てて家の中に入っていった。
そんなご挨拶をした次の日も、その次の日も、二人の凧揚げ訓練は続いた。直人は帰りの会の後、皆が帰る中で一人廊下で黙って立っている。友人とのお喋りを終えた篤志が、「俺んち行こう」と呼びかけるのを待ってまた一緒に山を越えるのだ。
「俺の凧、白いまんまやと地味かな」
ある日、木陰で直人持参のお菓子を食べながら休憩していた時のことだった。直人は、虹が描かれた凧を見ながらそう呟いたのである。
「まあ確かに大会で悪目立ちするかもね」
「まだ行くって決めてへんから!!」
直人はプイっと横を向いた。練習を始めて一週間がたったこの時、彼はもう凧揚げができるようになっていた。篤志は笑って肩をすくめた。
「はいはい分かったよ」
翌日の朝、二人で図工室に向かった。
図工の先生は珍しい組み合わせに驚いたようだが、にこやかに笑って二人を迎えてくれた。
「どうしたの二人で」
「武村君が、凧に絵を描きたいみたいなんです」
「そっかそっか」
制作当時に無地を気にして声をかけても「めんどいんでこのままでいいです」の一点張りだった直人。どうやら新しい友達に良い影響を受けたらしいと先生も嬉しく思った。
「じゃあマーカー用意するね。8色セットでいいかな?」
「黒だけでいいです」
「黒だけ?」
「はい」
「武村君、もっと色使わないの?」
「使わへん。あと上野、お前の凧見して」
二人の少年は図工室特有の角ばった椅子を隣に並べて腰かけた。ごつごつした木の机の上で直人は絵を描き、横から篤志が覗き込んでいる。本来なら固いやら座りにくいやら居心地の悪いそこで二人は時折顔を突き合わせ、出来上がっていく凧や凧揚げのことで熱心にお喋りをしていた。
「ここ、あんま線太くせえへん方がいいかな」
「えー・・・難しい」
「ふん。凧揚げるの上手くても、絵のセンスはないな」
直人はめんどいなんて言わなかったし、篤志も手持ち無沙汰に感じなかった。図工の先生も、授業の準備を邪魔されたなどとはつゆほどにも思わず、二人が寄り添う様子を優しく見守っていてくれた。
凧の絵は、授業時間を挟んで放課後に完成した。その日は遅くなったのでもう訓練はせず、そのままそれぞれの家に帰ることにした。二人の凧は、人気のない図工室の前の棚に仲良く並べられた。
直人の腕前はぐんぐん上達しているし、この凧が飛ばせるかどうかの確認が済めば、胸を張って大会が来るのを待てる。全てが順調に進んでいるかに思われたがー。
その翌日の朝、事件は起きた。
教室で、取っ組み合いの喧嘩が起きたのである。否、取っ組み合いではなく片方がもう片方に馬乗りになって一方的に激しく殴りつけていた。殴っているのは直人、殴られているのは篤志である。直人の目は吊り上がり顔は真っ赤だった。彼は無抵抗の篤志の体を殴ったり、髪の毛を掴んで頭を床に叩きつけたりしていた。時折「よくもよくも」と罵倒の言葉を浴びせ、まったく静まる様子を見せなかった。
直人のいまだかつてない激しい剣幕に、周りの生徒は恐怖のあまり誰も近寄れず、口々に制止の言葉をかけることしかできなかった。
騒ぎを聞きつけた担任が直人を取り押さえた時、彼は抵抗しながら甲高い声で叫んだ。
「よくも俺の凧壊したな、上野!!」
「っ・・・」
「でももう別にええもんな、これで凧揚げ大会出なくて良くなったんやからな!!」
二人は引き離され、直人、篤志の順で担任に別々に事情を話すこととなった。
「朝、学校に着いて図工室の前に言ったら俺の凧がなくて。それで教室に行ったら、上野が破れた凧持ってて、『俺が壊した』って言ったんです」
篤志の方も容疑を否定しなかった。
「はい、僕が壊したんです」
「なんでそんなことしたの」
「・・・朝、クラスで武村君の噂をしている人たちがいて・・・」
□□
その日、篤志は日直なので一人だけ早く学校に来ていた。水やりなどの当番をこなしていると、何名かが登校してきて凧揚げ大会の話を始めた。最初は楽しみだと言って笑いあっていたが、「でもさ」の一言で風向きが変わった。
「武村、来るのかな」
「えーどうだろ」
あの騒動の翌日、直人はいやいやながら他クラスにまで謝った。彼を馬鹿にしたことについて、先生達は学年全体に注意した。それで片が付いたと思われたが、あの時の「頭悪い」発言をなおも快く思わない者はいた。特に、馬鹿にしていた張本人ーまさに今話している彼らーがそれであった。
「来なくていいよ。下手だからクラスの足引っ張るだけじゃん」
「確かにー」
「プライドだけは高くてめんどいしさ」
「凧も真っ白でやる気ないくせに、俺らの大事な行事のジャマすんなっての」
「そんなこと言うなよ!」
篤志はじょうろを投げ出し、彼らに食って掛かった。
「武村君のこと、邪魔者呼ばわりするな!!」
「なんでお前がキレんの」
「俺は知ってるから! 武村君はもう下手じゃない。練習して上手くなって、今はもう凧揚げ大会やる気満々なんだからな!」
「は? 嘘つくなよ。あいつがやる気なわけないだろ」
突然割り込んできた篤志に困惑しながらも、彼らは悪びれる様子を見せない。
「嘘じゃない! 毎日、俺の家で練習してるんだ!」
「嘘、絶対嘘。証拠あるんなら見せろよ」
□□
「それで・・・武村君の凧を見せつけてやろうと思ったんです。あいつが頑張ってるって、やる気だって分かってほしくて・・・」
篤志は、図工室の前に置いてあった凧を教室に持って行こうとした。しかし途中の階段で凧を踏んづけてしまい、よろけた篤志の体もろとも凧は階段に叩きつけられた。ビニール製といえどそれではひとたまりもない。
うなだれる篤志を保健室に残し、担任は直人を待たせてある別室に向かった。
「俺、凧揚げ大会出ません。別にいいんです。最初から別に行きたくなかったですから」
「そんなこと言わない」
唇をかんでそっぽを向いている直人を、駆けつけてきた図工の先生がなだめている。
「最初から行きたくないなら、なんで上野君にあそこまで怒ったの? あんなに楽しそうに凧を作ってたじゃない。いっぱい練習もしたんでしょ。ホントは、大会に出たくないなんて思ってないでしょ。」
直人の視線が揺らいだ。何かを思い出すかのように宙を見つめている。
「でも、だってもう・・・」
いつになく弱弱しく声を絞り出す直人。その目線は部屋の隅の壊れた凧に向けられた。
「先生」
担任は足を踏み入れた。
「凧キットまだ残ってますか?」
「ないです。でもね」
図工の先生は明るい声を出して直人を見つめた。
「凧、ビニール袋で簡単に作れるのよ。今日三時間目、自習だったよね。教えてあげるから一緒に作ろう」
「それがいい。そうすれば凧揚げ大会に出られる。上野と一緒に凧揚げできるぞ」
担任は先程の篤志の述懐をそっくりそのまま伝えた。直人は黙って聞き、何かをこらえるように口を引き結んで天井を見やった。
「あいつも良くないことをしたけど、武村のことを想っての間違いだったんだ。許してやってほしい」
「・・・」
担任はぐちゃぐちゃになった凧を見つめた。ビニール部分が派手に破れ、骨も折れて剥がれ落ちている。だがどれだけ破損していても、そこに描かれたものはなおも力強く存在を主張していた。
白地の上に黒い縞模様、黒で縁取られた大きな目と鋭い牙、ふさふさとした毛並みを表現する黒いギザギザ。直人が凧に描いたのは、ホワイトタイガーの顔面である。
「なんでホワイトタイガーにしようと思ったんだ」
「あいつも・・・上野も、虎だったからです。俺、俺・・・」
凧を見つめる直人の目は潤み、声は震えを帯びた。
「俺、あいつと一緒に、同じくらい高く揚げたくて・・・」
「大会で、か」
直人は返事をしなかった。鼻をすすり、目から雫を滴らせる。だがその無言が、担任の言葉を肯定した。
「武村君」
図工の先生は直人の手を握った。
「上野君は悪いことしたけど、先生はもっと良くなかったわ。あんな誰でもすぐ持って行ける場所に凧を置いてたんだから。本当にごめん」
「いいえ。違います」
直人はぶんぶんと首を振った。
「先生は悪くないです。悪いのは全部上野です。あいつに全責任があるんです」
「武村君・・・」
篤志のせいだと言う直人の声は、元の気強さを取り戻していた。そしてその乾ききらぬ目には、何かの決意が込められていた。
「だから俺、あいつに責任取ってもらいます」
ーー
放課後になり、篤志は一人トボトボと廊下を歩いていた。今日はあの後ずっと保健室で寝ていた。保健の先生が色々気遣って話しかけてくれたが、うわの空でまともに返事もできていなかった。
(俺、俺、なんてこと・・・)
感情に任せ、取り返しのつかないことをしてしまった。直人に凧揚げ大会に参加してほしくて今日までやってきたことを、他の誰でもない自分自身で台無しにしてしまった。直人は大会に出られなくなってしまった。自分のせいで。あの時の自分を責めても責めきれない。
どん、と誰かにぶつかった。地べたを見ながら歩いていたから、前に人がいることに気づけなかった。ごめんなさい、と謝ろうとしてそこに立っていた人物を見て息をのんだ。
「武村君」
「上野」
直人はちらりと篤志を一瞥し、閉じていた本をパタン、と閉じた。彼が口を開く前に、篤志は頭を下げて大声を出していた。
「ご、ごめんなさい! せっかく作った凧を俺、壊しちゃって・・・。ホントに、ホントにごめんなさい!」
「俺こそ・・・」
「え」
「あんなに殴って・・・悪かったな」
ぼそりと呟かれた謝罪の言葉。自分の罪を責め続けていた篤志にとって予想だにしない言葉だった。
「そ、そんなこと気にしなくていいよ。悪いのは俺なんだから・・・」
「せやな。一番悪いのはお前や」
一転し、高飛車な口調になる直人。
「責任感じるんやったら着いてこい」
くるりと背を向けて歩き出す直人。篤志は戸惑いつつもその後を追った。
連れてこられたのは運動場だった。運動場の真ん中に、図工の先生と担任が立っている。それぞれが手に持っているものを見て篤志は息を吞んだ。一つは篤志の凧だった。そしてもう一つは。
「お前に壊されたから、俺自分で作る羽目になったんやぞ」
篤志とは全く違う形をした凧。そしてそこに描かれた、元の凧とは全く違うもの。凧が風に吹かれてひらひらとはためくと、描かれたそれがまるで生きて動いているかのように見えた。直人は走って行き、二つの凧を受け取って帰ってきた。
「一から作ったの?」
「そう。まだ揚げれるか分からんから、今から練習タイムや。お前も付き合え」
「え」
「・・・体が痛むんやったら明日でもええけど」
「そ、そうじゃなくて」
差し出された自分の凧を前に、篤志は躊躇いの眼差しで直人を見た。
「いいの? 俺なんかと一緒に練習しても。だって俺、武村君の凧壊した張本人だよ」
「・・・責任取れって言ったやろ」
直人は凧をぐいと突き出した。
「俺の凧を壊した責任。それから凧揚げ大会に誘った責任。お前のせいで俺、大会行く羽目になったんやからな」
「! わ、分かった!」
篤志は自分の凧を受け取った。そしてやっと直人にいつも通りの笑顔を向ける。
「責任取るよ。一緒に練習しよう!」
「よっしゃ。じゃ、せーので揚げるぞ」
「どっちが高く飛ばせるか勝負だね!」
幾何学的な形の凧と、手作り感満載の凧。それぞれの手元を離れ、徐々に高く上がっていく。
「大会本番も絶対負けないよ!」
「それはこっちのセリフや!」
口から鋭い牙を覗かせる、黄と黒の縞模様のたくましい肢体の虎。青緑の鱗を持ち、長い尾と爪ですべてを包み覆わんとする龍。地上で応酬する二人が乗り移ったかのように、互いに競い合いながら空を駆け昇ってゆくのだった。
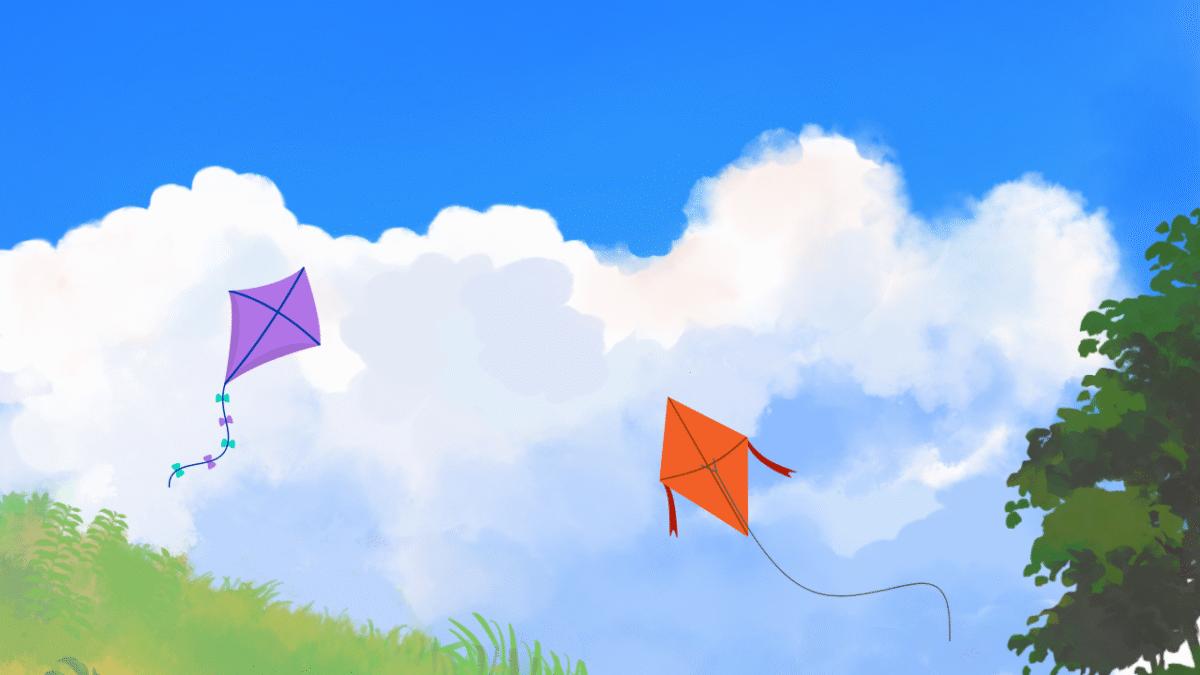

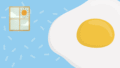
コメント