「なんで急に誘われなくなったんだろうね」
月曜日ービュッフェ予定だった日曜日の翌日ー、朝食の席で父親は首を傾げた。
「分かんないよ・・・もしかしたらただの女子あるあるなのかも」
「女子あるある?」
「うん。一回誘いを断ったら、もうあの子は次から呼ばなくっていいやってなるやつ・・・。なんか、女子同士の仲ってそういうものな気がするよ」
言っていて辛かった。もう何回も遊んでいるのに、そんな何気なく仲間外れにされたかもしれないと思うと。
「でもその子達、そういうことしそうにないけどな・・・これまで、ゲーム初心者の葵に教えながら遊んでくれてたんでしょ」
母親はレモネードをお代わりしながら葵を見た。
「じゃ、じゃあなん・・・」
「聞いてみればいいじゃない。隣のクラスに行くなり。電話するなり」
「それはっ・・・いいよ、そこまでは・・・。ご馳走様」
葵はそそくさと立ち上がり食器を流しに置いた。廊下に置いていたスクールバッグを引っ掴み、玄関から出て学校に向かう。
確かに聞けば早い。だがそんなことをしようとは思わなかった。他クラスに入るとか、自分から電話を掛けるとか、そんなことができるのは陽キャだけだ。
(それに、それに、もしかしたら・・・)
葵の頭の中には、「女子あるある」の他にもう一つ答えがあった。
(私が、ボードゲームオタクだってバレたんじゃ・・・)
それで三人に幻滅されたのではないか。
もう幾度となく頭の中に蘇る小学生の頃の悪夢。
『ボードゲーム? ・・・え~、空山さんってこーゆーの好きなんだー』
『なんか、おじさんみたいだね』
『つまんなそー、そんなのやめて鬼ごっこしよー』
小学生の頃、人を家に呼んだ最初で最後の日だった。翌日には、
『もうあの子を入れて遊ぶのやめない?』
『そーね、鬼ごっこしよって言ったら、嫌そーな顔してたもんね』
『あの子、中身がおじさんだからしゃーないね。ノリ違うんだもんね』
聞いてしまったのだ、偶然。自分への悪口を。
ボードゲーム好きは友達などできない。それが、葵が身をもって知った現実だった。
(眞代ちゃんも萌々ちゃんも翠ちゃんも、口に出さなかっただけなんじゃ。内心は『実はボードゲーム好きなんだ。なんかダサい』とか『テレビゲームよりもボードゲームが好きならウチらと合わない』とか思ってたのかも・・・。それで、それで、なんかノリが違うからもう誘わないってなったんじゃ・・・)
考えれば考えるほど、そんな気がしてならない。
(あの日、ボードゲームを勧めたけど、ボードゲームが好きだなんて一言も言ってない。だから、大丈夫。バレてない。きっと大丈夫。大丈夫・・・であってほしい。でも、でも急に誘われなくなった理由が他にあるわけないし・・・)
学校に着いた葵は周囲に目を光らせ、こわごわ廊下を進んで一息に教室へ飛び込んだ。
(トイレ以外、なるべく外に出ないようにしよう・・・。帰りの会が終わっても、すぐに帰らないようにしよう。だって鉢合わせるかもしれないもの)
三人と顔を合わせるのが怖かった。いったいどんな顔で葵を見るのか、不安でたまらなかった。どうか会いませんようにと天にも祈った。
幸いなことに、哀しいことに、葵が三人を見ることすらなかった。前のように葵はずっと一人きりだった。
(やっぱり、ボードゲームのことなんて口に出すんじゃなかった・・・)
そんな後悔の念を抱きながら、葵は問題の日ー先々週の木曜日ーの自分を責め続けた。
◇◇
問題の木曜日の前日ー水曜日。
学校から帰った眞代は、自室に入りスクールバッグから教科書とノートを取り出した。
ヴヴッ。棚に立てかけてあるスマホから振動音がした。手に取ると、メッセージが一件届いている。手芸部のトークルームで、送信者は部長だ。
『来月から、各自ケーキセットを作ってもらいます。モデルにする写真なり、イラストなりを探しておいてね』
『了解です』と打つ。同時に別のメッセージが届いた。
『何のケーキにしようか迷うな~。眞代ちゃん、明後日一緒に、駅前のあのおしゃれなカフェ行ってみない?』
『いいね、行きたい! 誘ってくれてありがと! 待ち合わせ時間なんだけど・・・』
メッセージを返すと電源を切り、スマホを棚に戻す。そして今度こそ机に向かった。
まずは今日習ったことの復習を各教科十分ずつ。その後宿題を済ませ、最後に明日の予習を五分ずつやれば勉強はおしまいだ。
教科書とノートをバッグにしまった眞代は、再び棚のスマホを手に取った。
「『キラ殺・森ステージその4』だっけ・・・」
人気配信者『0-jam』の『キラーを殺せ』の実況動画だ。萌々が、「参考になるよぉ」と勧めてくれた動画だ。
「動画時間は32分ね、よし」
スマホ一日一時間のルールには抵触しない。そのことを確認できたので動画を再生する。
動画を見た後、棚にしまっておいたノートを開いた。『Sir. Bibal』を前回皆で進めたところまでのあらすじをまとめたものだ。眞代の家にはゲーム機の類が一切ないので、一人でゲームを練習したりデータを閲覧したりできない。こうやって動画を見たりノートに書いて覚えたりしておかないと、次回から楽しくゲームをするのに支障が出てしまうのだ。
さっとノートを見返した後は、全部片して読書の時間だ。『イソップ寓話』の続きを読み始める。
ページをめくり、ページをめくり、気が付くと二時間が経とうとしていた。少し名残惜しく思いつつも、眞代は栞を本に挟み立ち上がった。
流石にお腹が空いた。作り置きのおかずで一人夕食の時間だ。
ーー
問題の木曜日の四日後ー月曜日。葵不在のゲーム会が行われた日。
「じゃーね、眞代ちゃーん」
「はーい、また今度」
一緒に登校した先輩と階段で別れ、自分の教室に入った眞代。既に来ていた萌々と翠が眞代に気づいて手を振った。
「おはよ、マッシー」
「おはよう、眞代」
「おはよー、二人とも」
手を振り返して席に着く。今日も二人と一緒に遊ぶ予定だ。三人で。
「葵ちゃん、来れないなんてな・・・」
四人で遊ぶのはとても楽しかったから残念だった。用事が入ったのなら仕方ないが、三人より四人の方がずっと楽しいのに。
じゃあ今お喋りしに行っちゃおうかな、と眞代が立ち上がった時だった。
「おはー眞代ちゃん」
「ちょっと助けてえ」
クラスの女子二人に引き留められてしまった。
「昨日のスーガクの宿題分かんなかったの」
「ノート写させてー」
「それは駄目だよ。解き方教えてあげるからノート開いてみて」
「えーん。だって三限目に提出だよぉ」
「大丈夫、これ全部、同じ公式使えば簡単に解けるから。・・・ほら、これとこれ代入してみて」
「・・・あっホントだー」
「あーん、頼もしいよ眞代ちゃーん」
いつも通り忙しい日だった。朝から夕方までクラスメイトの相手に追われ結局葵と話す時間はなかった。少しがっかりしながら帰宅。
宿題だけ済ませると、手提げバッグにお菓子を入れた。萌々の家に向かわなければ。
だが家を出ようとしたその時、廊下の黒電話が鳴った。
「はい、もしもし」
「あ、マッシー? モモだよモモ」
「どうしたの?」
「ごめん、今日うちで遊ぶのダメになっちゃった。ママが早く帰ってきて家で仕事するって」
「あらら。それじゃあどうする? 葵ちゃんもいないし、今日は中止する?」
「うーん、マッシーの家ダメなの?」
「私の家? あー、MSG持って来てゲームするってこと?」
「そーそー。ダメ?」
「うーん」
眞代は壁の時計を見た。今三時半。あと一時間半は家に眞代一人か。
「まあ、五時までで良ければうちで遊ぶ?」
「おっけー、すぐ行くね」
「翠は? 今日、金曜の振替で部活だよね? どうやって伝える?」
「今日は短いって言ってたから、もう終わるんじゃないかなぁ。モモがミドリンの家の前で待ってて、一緒にそっちに向かうよぉ」
というわけで、十分後に萌々と翠が眞代の家にやって来た。
「眞代、トイレ借りるね」
「はーい、どうぞ」
「マッシーんち、久しぶりぃ」
靴を脱ぎ、上がった萌々は周囲をきょろきょろ見回した。
「ホントなんていうか、昔ながらっていうかー、お侍のお屋敷って感じだよねぇ」
「そう?」
「なんか、お金持ちが住んでそうー」
瓦葺きの屋根、木造の壁、平屋建て、所々に設えられた和式の調度品。そしてまあそこそこ広い。古風なのはその通りだが、お屋敷はいくら何でも言いすぎだ。
「萌々だって、もうしばらくしたら大きい家に引っ越すって言ってたじゃない」
「まぁねー、完成したら遊びに来てねぇ」
「ありがとね」
眞代は二人を、玄関を右に曲がって突き当りの畳六畳の客間に通した。
「あ、かわいい」
萌々が、床の間の横の違い棚の置物に近寄っていく。赤、ピンク、白を基調としたダルマがそれぞれ二体、計六体並んでいる。
「いいなぁ、萌々こういうの好き!」
「作り方教えてあげようか?」
「あ、ううん。それはいいや。てかこれ、マッシーの手作りなの?」
「うん、左三つは私が作ったの。部活で」
刺繡糸で模様を縫い、フェルトに綿を詰めて作ったものだ。目は、ボタンを縫い付けてある。
「器用だねぇ、流石手芸部」
バリバリバリ。
翠はもう、一人で卓上のせんべいを食べ始めている。
「ミドリン、フライングー」
「部活終わりだから栄養補給してるだけ」
「ふーん、頑張ったんだねぇ」
「てかさ」
翠は二つ目のせんべいに手を伸ばしながらモモをちらりと見た。
「別にいいんだけどさ、萌々は部活に興味なかったわけ? 何も入ってなかったよね」
返答に窮したのか萌々は一瞬黙ったが、すぐにニコッと笑った。
「もーミドリン分かってるくせにぃ、部活ってモモには向かないのぉ」
「ま、まあ、入りたいのがないのなら無理することないよね」
「そーそーマッシーの言うトーリ」
萌々はくるりと違い棚に背を向けるとバッグをごそごそと探った。
「ねぇ、そんなことよりゲームやろーよぉ。もうあと一時間ちょっとしかないんでしょ?」
「確かに、時間は無駄にできない」
翠は頷いてバッグから二つのMSGを取り出した。
「眞代はこっち使って」
「悪いね翠、お姉さんにもお礼伝えといてもらえる?」
「別に良いって。姉貴はもうゲームしないんだから」
翠はそっけなく言うと、彼女の姉のMSGを眞代の方へ押しやった。
電子辞書のような外見の三つのMSGが起動し、ゲームを選ぶ画面になった。
「『サーバ』はナシね、ストーリー進めたら葵がついてこれなくなっちゃう」
「同感。じゃあ、『キラ殺』とか?」
「モモもそれが良いなぁ、今日は定番の森ステージで行こっか」
キラーの役をコンピュータに割り当て、眞代達三人は逃走者側でゲームを始める。
『キラーを殺せ』は、3Dタイプのアクションゲームである。殆どの人が想像するように、キラーと逃走者で殺し合うのだが、全員のゲームの画面が常にキラーの三人称視点という一風変わったゲームなのだ。
キラー1人がフィールド(今回は森)の中を縦横無人に走り回り、逃走者は基本的に自分の’避難所’の中から外に出ることはできない。フィールド内の木のうろの中、茂みの中など、逃走者は各々三つの’避難所’を選び、そのうち一つに身を潜めてゲームスタート。キラーが自分の近くに来たと分かったら’避難所’の中からキラーの命を狙う。
眞代はこのゲームがあまり得意ではなかった。なんせ、キラーの三人称視点しか映らないので逃走者側は操作が難しいのだ。まず、キラーが自分の’避難所’の近くにいるかどうかが分からない。
「あ、これキラー今私の近くにいる?」
そうと分かっても、攻撃を外すこといつもの如し。それでキラーに存在がバレてしまった。
防御する間もなく、キラーは茂みをかき分けて中にいた眞代の逃走者を引きずり出す。そして首を絞め始めた。MSGがいつものリモコンの代わりにヴンヴン唸り声をあげている。教えられなくても、生命の危機に瀕していることなど分かっているのに。
「ふりほどっ・・・あれ、MSGだと何ボタンだっけ」
焦っていると、不意にキラーの周りにモクモクと煙が立った。
「いまのうち、Zボタンで振りほどいてぇ!」
萌々が声を上げる。少し離れたところで争うキラーと黒人のマッチョ。
「マッシー、ワープゲージ溜まった?」
「あ、そうね、うん! 今ワープできるよ!」
「〈磁石〉でついてくから、別の’避難所’にワープしてぇ! 十字の右ボタンと1,2,3で好きなとこ選べる!」
「最初に決めた番号ね、じゃ、じゃあここ!」
3を押してツリーハウスを選ぶ。
画面にはキラー1人が取り残され、否、画面が遷移する。キラーもまた、二人と一緒にツリーハウスの中にいるではないか。
「あちゃー、〈磁石〉持ってたかあ。てかマッシー、ここあんま良くないかも」
「えっごめん」
キラーが短剣を取り出す。が、ほぼ同時に萌々がレイピアを抜くと、キラーはサッと飛びのいてツリーハウスの窓から外へ出た。
屋根によじ登ったキラーが、ポケットから爆弾を取り出した。窓からツリーハウスの中に投げ入れようとする。
が、刹那、その腕がレイピアで貫かれた。そのままマッチョの馬鹿力でキラーが窓からツリーハウスの中に引きずり込まれる。
「今、モモがワープできるよぉ! 今度はマッシーが〈磁石〉でついて来てぇ!」
「うん、オッケー!」
こうしてツリーハウスの中には、レイピアで床に固定されたキラーとカウントダウンする爆弾。
カウントダウンが「1」になると画面は鳥瞰図に変わり、ツリーハウスが木っ端微塵になる映像が流れる。そして画面には「The killer was killed」の文字。
「やったぁ、勝ったぁ! あれ、てかミドリンは? 生きてるよね?」
「治療してたらゲーム終わった」
「てことは、逃走者は全員生存だね。萌々のお陰だよ、ありがとー」
「へへっ、でしょぉー」
得意げに胸を張る萌々。本当に、萌々の判断力と瞬発力には毎度感嘆してしまう。
「二戦目どこにするー? アオイっちいないから、新ステージはやめとく?」
「そうだね、翠どこがいいとかある?」
「学校とか」
「いいね」
「さんせー、キラーはどうするぅ?」
ガチャ。
不意に玄関の鍵が回る音がした。眞代は目を見開く。今日はまだ、誰も帰ってこないはずなのに。
ペタペタと廊下を歩く音がする。それで、誰が帰って来たのか眞代には分かった。
「ごめん、弟が帰ってきたみたい。一声かけてくるね」
「はいはーい」
「早く戻ってきて」
眞代は客間を後にし、台所の方へと向かった。案の定、そこには一つ年下の弟がいた。やかんに水を入れ、火にかけている。
「お帰り」
「ああ、姉さんか」
弟は眞代に背を向けたまま言った。
「誰か家に来てるの?」
「友達二人。五時くらいまで客間で遊んでるよ」
「フーン、そう。僕は自分の部屋で真面目に勉強してるから、大声出して邪魔するのだけは勘弁してよ」
弟はそれだけ言うと口を閉ざし、茶葉をどれにするか選び始めた。
「下の引き出しに、隣町のお茶屋さんの茶葉があったはずだよ」
「・・・」
弟はそれを聞くと火を止め、上の引き出しからスーパーで買った水出し茶を取り出した。
「冷茶でいいや」
弟の様子に、眞代は少し違和感を覚えた。彼が眞代に対してそっけないのはいつものことなのだが、それにしてもなんだか今日はちょっととげとげしすぎる気がする。
そういえば今日は、友達の家で遊んで帰ると言っていた。それがこんなに早く帰って来たということは、そこで何かあったのではないか。
弟は、無言で眞代の横を通って台所を出て行こうとした。
「あのさ、夜になったら私、話聞けるよ」
応答はない。それでもその背中を声で追う。
「私じゃなくても、お父さんとかお母さんでもいいから。何か困ってるなら相談してほしいな」
弟は振り返りすらせず、廊下の角を曲がっていなくなった。眞代は後ろ髪を引かれながら台所を出た。
ああ言っても、実際に弟が眞代に何かを相談したことなど一度もない。それでも言わずにいられなかった。
「っさてと。でも今は、友達と遊ばなきゃ」
頬をパン、と叩いて客間に戻る。ゲームの再開だ。二戦目もキラーはコンピューターだが、強さはさっきより上げてある。
「キラーこれ、どこ走ってるのかな。私の’避難所’の近くではないとおもうんだけど」
「あたしんとこでもない。てか、この辺どれもいないでしょ。こんなところでウロウロして、何やろうとしてるわけこいつ」
「あーモモ分かったかも」
「え」
「ホント?!」
「うん、キラーの狙いはねぇ」
「たつたのかわのにしきなりけり!!」
三人は、一斉にMSGから顔を離した。客間にしん、と静寂が訪れる。目線が互いに交わった後、自然と一点に集中した。襖の奥、すなわち客間の外の廊下。甲高い声の主がいる方だ。
「ちょっとごめん、離脱するね」
断りを入れ、眞代は襖を開けた。
「えーっと、次は『あきのたの・・・』」
「ちょっと何してるの」
「見れば分かるでしょ、百人一首だよ?」
客間の前で座り込む弟。その周りには、下の句の書かれた札が廊下いっぱいに並べられていた。
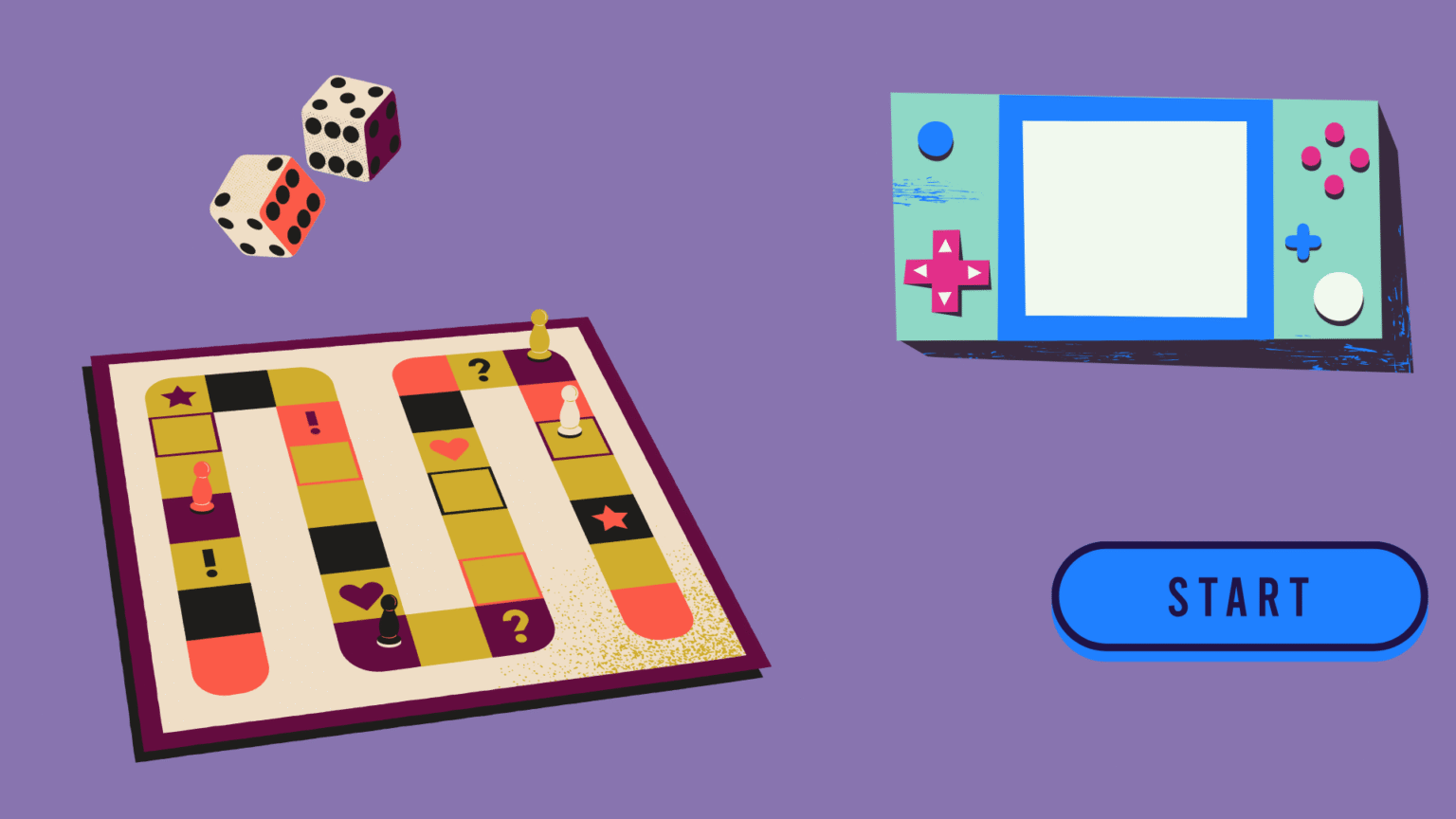
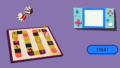
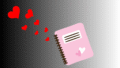
コメント