「ようこそアオイっち~」
ドアが開けられ萌々の顔が覗く。玄関からはフローラルな香りがした。
きちんと揃えて並べられた靴と、靴箱の上に飾られたピンク色の造花、後ろで手を組んでこちらを見ている萌々。
(よその家にお邪魔するってこういう感じなんだ)
「お、お邪魔します・・・」
「さあ上がって上がって! もう皆来てるよぉ!」
「う、うん」
靴を脱ぎ、こわごわ萌々の後について歩く。緊張している。今自分は、他人の家にいる。未だに実感が湧かない。
(まさか私が誰かの家に遊びに来ることになろうとは・・・)
手を洗い、リビングに入る。白を基調とした部屋で、所々にベージュやパステルカラーの家具が置かれている。
フローリングの床には丸いカーペットが敷かれ、その上にミニテーブルがある。眞代がミニテーブルにお菓子やジュースを並べていた。一方、壁にぴったりつけられたベージュ色のソファーの上には翠がどっかと座っている。その手には数枚の青いプラスチックケースが握りしめられていた。
(人に言葉を掛けるってどうやったらいいんだろ・・・)
先に葵の存在に気づいたのは翠だった。が、彼女は無言で目線を手元に戻す。中身が何かは分からないが、とにかくケースを見比べるのに夢中なようだ。
「あ、来た来た葵ちゃーん」
遅れて葵に気づいた眞代がにっこり笑いかけてきた。
「大丈夫? 迷わなかった?」
「う、うん。ごめんね遅くなって」
「全然そんなことないよ、大丈夫!」
座って座ってというようにカーペットを指す眞代。おずおずと腰を下ろす。ピンク色のカーペットはふわふわしていて、葵の膝を柔らかく受け止めてくれた。
「アオイっちがクッキーとキャラメルポップコーン持って来てくれたよー」
新たに大皿を持って萌々がリビングに入ってくる。テーブルに置かれた皿を見て翠が「あれ?」と言った。
「手作りじゃないの?」
「うん・・・市販のやつ」
(だって、遠足から帰って来たばっかよ?)
「ちょっと翠、さっきまで遠足だったんだよ。作って来れるわけないでしょ」
眞代はポップコーンをプラスチックのスプーンで自分の皿に取り分けた。
「このポップコーン好きなんだよね。あ、私の持ってきた梅ゼリーも食べてね」
「あ、うん。頂きます」
小袋を破って丸い常温のゼリーを口に入れる。梅の果肉を練りこんだゼラチンが砂糖でコーティングされている。噛み応えがあり、程よく酸味が抑えられていて甘い。
(これも心の栄養・・・)
甘いものを口に入れたお陰か、少し緊張が和らいだ。
「早くやろうよ」
翠は菓子に見向きもせず、反対側の壁の前に置かれたテレビを指した。
「そーだね、やろやろー。どれにするか決めたぁ?」
萌々がテレビの前に行き、何かを探し始めた。まさかバラエティー番組でも見るつもりだろうか。だとしたら全くついていける気がしないのだが。
「葵ちゃん、大丈夫?」
ジュースを飲んだ眞代が尋ねてくる。
「これからゲームするつもりなんだけど」
「ゲーム?!」
思わず目を見開いていた。心臓がうるさく音を立て始める。
(まさかこの三人もボードゲームを?!)
パラッピラッピンポーン!
突然、テレビからポップな音楽が流れてきた。カラフルな画面に、三頭身の小人っぽいキャラクターが集合している。その下には、”Let’s begin game”の文字。
(ゲームって、テレビゲームのことかあ・・・なあんだ)
「はいこれ」
翠が小さめの白いリモコンを差し出してきた。十字のボタンやA・Bのボタン、キノコのような突起が付いている。
「葵、4Pね」
「よんぴー?」
「あれ、葵ちゃんもしかしてゲーム初めて?」
「う、うん」
(別のゲームは熟練者なんですけど)
「そっかあ。じゃあ・・・そうだね、しばらくは難易度を『Easy』にして、コースもやりやすいのにしない?」
眞代の問いかけに対し、萌々は「いいよぉ」と即答したが翠は黙ったままだ。
「葵ちゃん、ゲームやったことないんだよ? いきなり難しいコース行っても付いて行けなくて楽しめないじゃん」
「・・・分かった」
しぶしぶといった表情で了承する翠。眞代は更に言葉を繋ぐ。
「四人でやるの、初めてじゃん? プレイの仕方も変わるだろうし、しばらくは四人の時用の戦術を考える時間にしたらいいじゃない」
「なるほど、それはあり」
翠は、今度は納得したような表情を見せる。葵もホッとした。
(良かったあ、私が三人の邪魔してるみたいにならなくて・・・)
「じゃあ、早速やろー」
萌々がリモコンのボタンを押すと画面が切り替わった。空の上らしき背景。橙だから、時刻は夕暮れだろうか。左端には小人が四人並んでいる。色が上から、ピンク、黄緑、白、水色。
“Start”の文字がフェードインしたかと思うと、上の三つの小人が動き出した。
(あれ、いきなりゲーム始まるんですか? ルール説明とかなし?)
「安心して、葵ちゃん。これ練習だから」
「あ、そうなんだ」
「説明するね。葵ちゃんは4Pだから一番下の小人だよ。これを、右へ右へと動かして進めていってほしいの」
「えっと・・・ボタンはどれとどれを使えば?」
「画面上に操作方法が出てるでしょ。そのボタン長押しで・・・そうそう、動くでしょ。進んでいったら途中で宝石のピースとか、攻撃してくる敵が出てくるの。でね・・・」
練習中、眞代が一つ一つレクチャーしてくれる。別のボタンで小人は弾を発射する。弾数は無限。長押しして進みながら撃ち続けられる。これで敵を倒す。宝石のピースは通過するとゲットでき、五つ貯めると一つの宝石になる。練習を経てなんとかそれは覚えることができた。
「翠、ボムとかお邪魔アイテムって練習では使えなかったっけ?」
「コマンドは出てるからそれ見て覚えれば?」
なんか、強い攻撃とか他プレイヤーの妨害もできるらしい。・・・まあとにかく、倒した敵の数と完成した宝石の個数が主なスコアとなる。それを四人で競うらしい。
「葵ちゃん、行けそう?」
「まあなんとか?」
「それじゃあ本番行くよぉ」
萌々の一声で再び画面が切り替わった。夕暮れの空に”Game Start”の文字がフェードインし、左端からのスタートだ。教わった通りに、右へ右へと移動しながらとにかく敵を倒し宝石のピースを拾い集める。
(練習のまんまじゃん。なんとかなりそう)
だがそう思えたのは最初だけだった。
途中から空の様子が変わり始め、明らかに難易度が変わった。雲が障害物となって行く手を遮ってくるため、ぶつかって移動がスムーズにいかない。もたついていたら、目の前のピースをかすめ取られる。敵も、弾一発で消えてくれないし攻撃も強い。倒しきれず、何とか避けて進むしかない。回避のため十字ボタンばかり使っていたら、ジャンプの仕方を忘れた。高所のピースが取れない。切り替えて進もうとしたら、なんと目の前に敵出現。
と、急に画面が暗転した。何も見えない。
(え、何?)
「あーちょっとミドリン!」
「これ、回避不能のやつじゃない! ずるい!」
「この時間、私は特殊モードだから。よし、これでちょっと差がついた?」
(あ、なるほど。今のはお邪魔アイテムか。 え、どうやったら使えるんだっけ?)
あたふたしていると、リモコンが震え、自分の小人が攻撃に当たる音がした。そこで画面が元に戻ったが・・・。
(あー宝石のピース全部なくなってる!)
そういえば、敵の攻撃に当たればピースは全て失われると言われた。なんと無慈悲な。
(と、とりあえずまた一からピースを拾わなきゃあ・・・)
雲に引っかかりつつも、上に下にと取りこぼしのないようにピースを拾いながら進む。
「あー、アオイっち遅れてるー」
言われて改めて画面を見ると、三人は遥か先に進んでいるではないか。
「ごめ、へ?!」
急に小人が操作できなくなった。ひとりでに前に進んでいき、三人の傍まで来るとやっと解放された。
「アオイっちー、画面は先頭の小人に合わせて動くんだよぉ」
(え、もしかして私遅すぎたの? だからこうなったの?)
気をつけなきゃ、とは思う。だがまたすぐピースを求めて、見切れて、運ばれての繰り返しだ。お邪魔アイテムも一方的に食らいまくって散々だ。
そうしてプレイ時間三分を経過した頃、画面中央で突然小人の動きが止まった。
(終わりかな?)
違った。画面右端から巨大な敵が姿を現し、攻撃してくるではないか。
(ひー)
強すぎる。葵はパニックになっていた。最早、弾を出すボタンがどれかも忘れた。攻撃する三人をよそに、ただひたすらに逃げ回る。
「『Easy』のボスってこんな弱かった?」
「これならボムもいらないよね、ミドリン」
(どこが?! あとボムって何?!)
死んでは復活してを繰り返し、最後に一発食らったところで三人の集中砲火がボスを爆発させた。フェードインする”Game Clear”の文字。続いて、成績らしきものが映し出される。
ビリは当然、葵。三位眞代、二位が萌々で一位は翠だった。
「あーん、キル数はモモの方が多かったのに」
「翠は宝石の数とボスダメージ量がずば抜けてるからね。どうだった、葵ちゃん?」
「いや、大変でした・・・」
疲労困憊で自分のスコアを見やる。どの数字も三位の眞代の三分の一にも及んでいない。惨敗も惨敗、ズタボロだ。
こんなズタボロ具合、その時初めて遊ぶボードゲームでしか経験したことはない。久しぶりの感覚だ。懐かしささえある。
(どうやったらもっと上手くできるかなあ・・・)
「あの、葵ちゃん、大丈夫?」
「え? 何が?」
考え込んでいると眞代が心配そうにこちらを見ていた。どうやら落ち込んでいると思われたらしい。
「第二回戦、行こーよぉ」
「あ、ちょっと待って。次なんだけどさ」
リモコンのボタンを押そうとする萌々を真白が制した。
「葵ちゃんがやりやすいように特別ルール作る?」
「え、何。葵に忖度するってこと?」
翠が露骨に嫌そうな顔をする。
「そうそう。私達三人はお邪魔アイテム使うの禁止とか」
「あ、そういうのは大丈夫」
誰よりも早く葵は即答した。惨敗とは言え、落ち込んでいるわけでも凹んでいるわけでもない。
(初めてやるんだもん、上手くできなくて当然)
「どうぞどうぞ、全力でやってもらって」
「え、いいの?」
眞代は戸惑っている。しかしこのくらい葵にとって当たり前だ。初心者なので難易度調整は必要だが、接待プレイなどは不要。葵の父親だって、ボードゲームで手加減することなど絶対しない。
「大丈夫。私、頑張ってついていくから」
「おお~さすがアオイっち」
笑う萌々。その声には少し感嘆が込められていた。翠は無言だが、僅かに目を見開いて葵を凝視している。
(認められてる?)
そう思うと、悪い気はしない。
「でも~アオイっち」
萌々がニヤッと笑い上目遣いで見てくる。
「頑張ってもすぐにはモモ達に追いつけないよ?」
「それは分かってるけど・・・」
「だから、アドバイスしてあげるっ」
「えっ」
「モモ頭良くないけど~ゲームは得意だから! それともいらない?」
「あ、ううん・・・もらえるなら下さい。さっきはとにかく何もかもが上手く行かなかったから」
「しょーがないなー。うーんとね、アオイっちまずスムーズに動けるようになれば?」
「そうだね。移動に慣れるまでは、敵の攻撃を避けることと宝石のピースを集めることに集中してみたらどうかな?」
「ふむふむ」
腑に落ちるアドバイスだ。それに、二人が自分のために考えてくれたんだと思うとなんだか気持ちがいい。
「分かった、そうする」
「いや、それだけじゃダメ」
不意にリモコンが取り上げられた。
「へ? み、翠ちゃん?」
「まずは移動に専念すべき。それはそう。でも同時に、全部のコマンドを把握するくらいは必要なんじゃない?」
「コマンドとは?」
「リモコン操作のこと。ボムとか、お邪魔アイテムの出し方とか。そういうの全部覚えておいてたまに使ってみるの。移動に慣れてきた頃に急にスムーズに使えるようになったりするわけ」
「ほ、ほう」
「さっきの感じ、葵は移動以外のコマンドを全然覚えてなかったんでしょ? 改善したいんならせめて頭の片隅には入れときなさいよ」
リモコンを持ったまま腕を組む翠。ツンと澄ましかえったような態度だが、その声は先程までとは違って張りがある。それに何より、今までよりずっと饒舌だ。眞代と萌々も呆気にとられたように彼女を見ている。
「このボタンとこのボタン同時押しでボムが・・・うーん、練習画面に戻る? いや、実際に使ってるところを見せた方がいいかな。今から三人でやるから見てなさいよ。別に、一回見学でもいいよね?」
「あ、うん」
(ところで、リモコン取り上げる意味あった?)
「じゃ、萌々、準備して。ステージは今のとこ。難易度も『Easy』のままでいいから」
「分かったよぉ。てかミドリンってホント、ゲームのことになると饒舌だよねぇ」
萌々が少し苦笑しながらリモコンを操作する。
「葵」
翠に名前を呼ばれた。目が合う。
「私の横に座って。リモコン操作と画面を照らし合わせてみて」
「わ、分かった」
まだ少し慣れない。が、新たな一面を見せてくれた彼女に近づいてみたいという気持ちが勝った。それに今ならなんだか大丈夫な気がする。ソファーの上、翠の横に座る。そこでしばらく、彼女のプレイを見学した。
見学後、また葵はゲームに参加したが、今度は翠がしばらく見学に回った。
「宝石のピースは、貯まる前にお邪魔アイテムかボムに変換しちゃいなさい。抱え落ちが起こるかもしれないんだから」
横からアドバイスしてくる翠。
「えっと・・・どっちが良いんだろ?」
「私のおススメはボムだよ、葵ちゃん。敵のキル数が一番スコア高いし」
「モモはお邪魔アイテム派。やられたらやり返したくなるもんねー」
「ホントは、バランス良くできたらいいんだけどね。ま、初心者のうちはボムが良いと思う。てか葵、私早く『Very Hard』に戻りたいからさっさと上達してよ?」
「ちょっと翠、無理強いしないの。葵ちゃんも、楽しむこと第一でいいからね」
(楽しんでるよ・・・うん、なんか楽しい・・・)
気持ちが高揚している。今までほとんど見たこともなかったテレビゲーム。やってみればこんなに楽しいとは。
いや違う、テレビゲームも楽しいが、一番楽しいのはこの雰囲気だ。
「うわ、アオイっちお邪魔アイテム使ってきたー」
「逃げなきゃ」
「ふーん、今のタイミングは悪くないんじゃない?」
(私、今パパ以外の人と遊んでる・・・)
父親と遊ぶときはとにかく安心感と充実感がある。それとはまた違う、ワクワクが止まらない弾けるような楽しさがある。
『ねぇ葵、パパと遊ぶのもいいんだけどさ。友達と遊ぶのもきっと楽しいはずなんだ』
(もしかして・・・これがそう?)
気遣ってくれる優しい眞代、明るい萌々、親身になってアドバイスをくれる翠。
三人は自分にとっての友達なのかもしれないと、葵はそう思ったのだった。
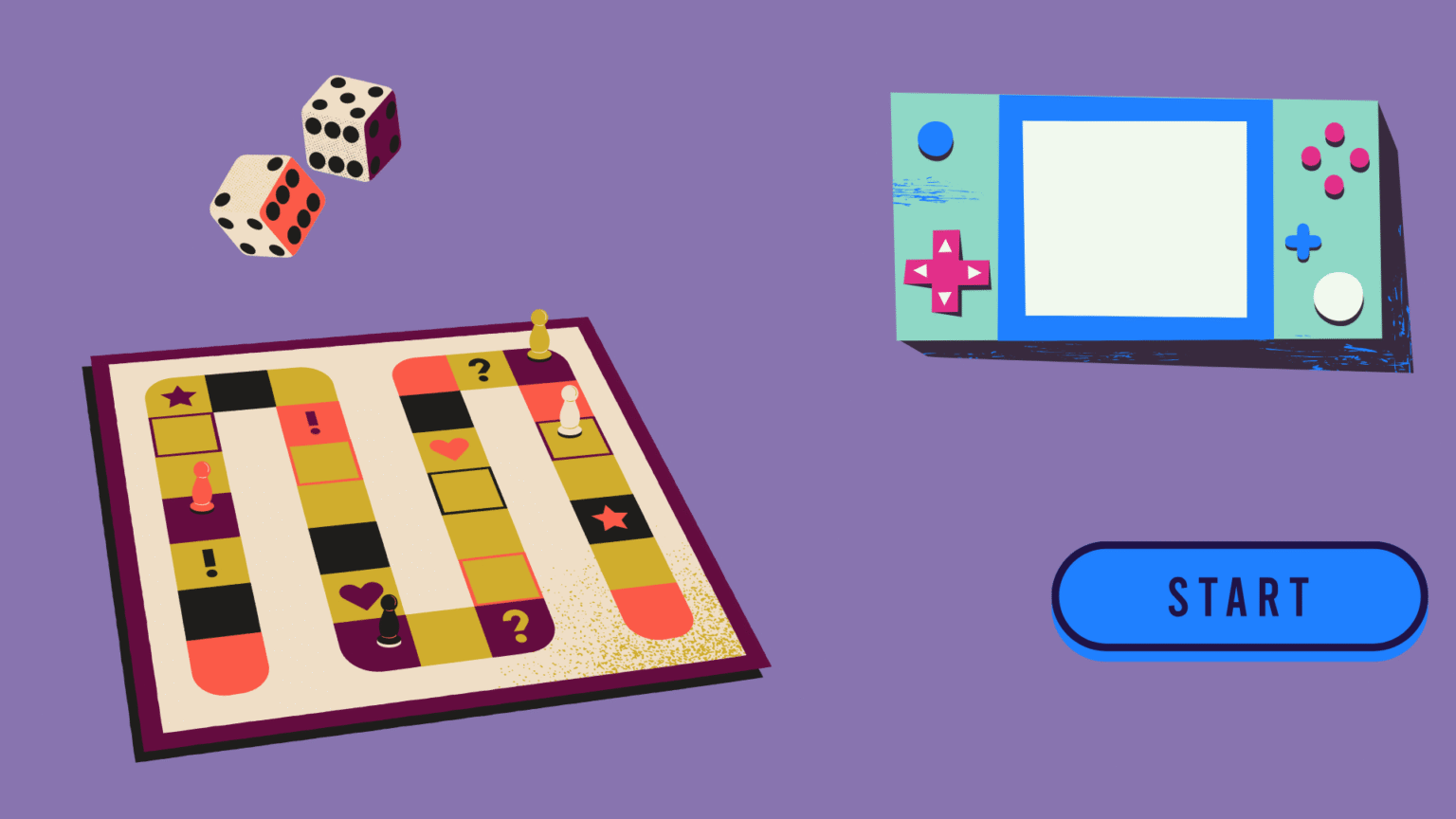
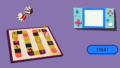

コメント