「一時半には公園の入り口に集合すること。では解散!」
教師の言葉が終わるや否や、体育座りで整列していた生徒はワッと歓声を上げて立ち上がった。
「一緒に食べよ!」
「うん、いいよ!」
「トーマ、あっちで食おーぜ!」
「いや、あっちのが良くね?」
「なっちゃん、どこー?」
生徒達は友人同士で合流し、広い公園のグラウンド中に散っていく。
一分もしないうちに、土の上にレジャーシートが敷かれ弁当が広げられていく。そんな中、空山葵は一人リュックをしょったまま公園の隅の方へと移動していた。
(あーやっぱ私、遠足嫌いだなあ)
否。中学生になったから社会見学だったか。まあどちらでも同じことだ。小学生の頃から嫌いなのだ、「仲良し同士の弁当タイム」が。
(友達いないんだもん、私)
人気のない場所に向かう間にも、仲良く固まったレジャーシートは嫌でも目に入ってくる。お喋りしたり、おかずを交換したり、大騒ぎしながら蟻を追い払ったり。
葵が彼らを見ているように、葵も彼らに見られているのだろう、きっと。早歩きで隅を目指す。
(ぼっち恥ずかしいよー。早く目立たないところに行きたいよー)
グラウンドの隅にちょうどいい木陰があった。早速レジャーシートを敷く。離れていても、キャッキャッと騒ぐ声が聞こえてくる。
(寂しいな。早く家に帰りたいよ・・・)
レジャーシートに腰掛けながら思った。普段学校にいる時もそうだが、今日はことさら強く帰宅を求めてしまう。家には一緒に遊んでくれる相手がいるのだから。
(でも今はぼっちよ。あーあ、誰か『一緒にお弁当食べない?』って言ってくれる優しい人はいないかなー)
「ねえ、一緒にお弁当食べない?」
「ファッ!!」
なんというデジャヴだろう。びっくりして振り向くと、そこに一人の少女が立っていた。すらりとした体格で、葵よりやや背が高い。目鼻立ちのはっきりした顔つきで、長い髪はポニーテールにしてまとめている。
(誰だろ? あー、隣のクラスの学級委員長だったっけな?)
「空山さん、一人だよね? 良かったら一緒にどうかなって」
よく通る声で、少し気遣わしげに問いかけてくる。
「あ、勿論嫌だったら無理しなくてもいいんだけど・・・」
「い、いえ、行きます・・・ありがとうございます」
思わず頭を下げていた。助かった、と思った。
(ぼっち飯回避ー。マジサンキュー、『隣の委員長』さん!)
「良かった。こっちだよー」
「はい・・・」
ガッツポーズしたくなるのをこらえ、神妙な顔つきで「隣の委員長」の後について行く。
向かった先は、グラウンドの真ん中あたりのレジャーシートだった。そこでは女子二人がおにぎりを頬張っている。パッと見て、どちらも知らない顔だと判断した。
「空山さん、来てくれたよ」
「おー良かったねぇ!」
「・・・」
ニコニコ笑うお団子頭の垂れ目女子と、黙っている色白のボブヘアーの女子。後者のリアクションは葵を不安にさせた。
(誘ってもらえて嬉しいけど・・・私と一緒だとやっぱり楽しくないよね)
「さあ座って座って!」
「隣の委員長」に促され、おずおずと畳んだレジャーシートを地面に敷き直す。腰掛けると、彼女がずいっと身を乗り出してくる。
「改めて宜しくね。私、浜崎眞代!」
「梅野萌々だよぉ!」
「木村翠」
「そ、空山葵です。宜しくお願いします、浜崎さん、梅野さん、木村さん」
「んも~、固いなあアオイっちは。マシロ、モモ、ミドリでいいんだよぉ」
団子頭の梅野萌々が、いやいやと手を振った。
「ミドリンもマッシーもそう思うでしょ?」
「別にどっちでも」
「私は名前で呼んでほしいんだけど、ダメかな?」
「隣の委員長」こと浜崎眞代が首を傾げてじっと見てくる。
(いやー、初対面でいきなり名前呼び捨てはハードル高いよ?)
かと言って、名字呼びを続けるのも感じが悪かろう。
「ちゃん付けしちゃダメですか?」
「全然オーケーだよ」
眞代がパチリ、とウインクをした。
「ねーところでさぁ」
水筒のお茶を一口飲み、萌々が顔をパッと輝かせて話し始めた。
「昨日の『0-jam』の配信見たっしょ?」
「見たよー」
「見た」
「全キル、マジでカッコ良くなかったぁ?」
「よくあんな効率よく倒せるよねー」
「扉閉まる直前に相手の首を切るとこが特にすごかった」
(おっと、やっぱこういう話になりますか)
盛り上がる三人をよそに、葵は無言で水筒の茶を飲んだ。最近のトレンドやら、アイドルやら、ファッションやらには全く興味がない。
(白々しい相槌しか打てないだろうし、黙って見守っとこう)
もし話を振られたら「そういうのあんま詳しくなくて」と申し訳なさそうに答えればいいい。
「葵ちゃんはさ」
弁当の蓋を開けようとした時、眞代に話しかけられた。
「普段何して遊ぶの? 何が好きなの?」
「え、私? 読書かな」
実際、読書は二番目に好きなものだ。休み時間はずっと一人で本を読んでいる。
「何読むの?」
「グリム童話とか」
「しらーん」
「何それ」
いつの間にか萌々と翠も会話に加わっている。
「ヨーロッパの昔話だよ」
「ふーん」
翠は興味をなくしたように弁当を再開した。
「アオイっち、頭いーんだねぇ。モモ馬鹿だからそういうの分かんないや。あ、でね、ミドリン」
(だろうなー)
予想通りすぎるリアクションだ。これまで新クラスに上がる度に「読書が好き」と自己紹介してきた。第一印象としては微妙すぎたようで、その後葵の机に話しかけに来てくれるクラスメイトは現れなかった。
「どんなお話が入っているの?」
親切にも、眞代だけは質問を続けてくれる。
「うーんとね、『ガチョウ番の娘』、『千枚皮』・・・」
「うーん、知らないなー」
「『トゥルーデおばさん』、それから『ブレーメンの音楽隊』」
「あ、それ知ってる!」
眞代が手をパンと叩いた。
「動物がピラミッド組んで、盗賊を追い払うやつでしょ! 幼稚園の劇でやったわー」
「へ、へー。そうなんだ」
「はいじゃあクイズでーす。私、何の役だったでしょう」
「眞代ちゃんかあ・・・」
何の役だろう、と葵は考え込んだ。背が高めだから犬かロバだろうか。
(あーでも、幼稚園の頃から背が高かったとも限らないのか・・・)
「ねー何だと思う?」
「ね、猫?」
顔立ちからイメージした動物を答えた。
「ブッブー。正解はね、盗賊でーす」
「えー、そうなんだ」
「そうそう。黒い服着て紙のヒゲつけて、おもちゃの剣を振り回してたんだよー」
眞代は箸を持っていない方の手を握ってブンブン振った。全然イメージが湧かない。
「面白かったなー、あれ。小さい頃のイベントってすっごく印象に残るよねー」
(あーまあ確かにそうかも)
「葵ちゃんは何か劇やった?」
「白雪姫の劇」
(なお、これもグリム童話なり)
「何の役だったの? 白雪姫? 小人?」
「お妃」
白雪姫を妬み、殺そうとする継母お妃だ。
(紫のドレス&王冠セットから、黒コート&毒りんごセットへの衣装チェンジが少し大変でしたね)
「そっかそっか」
葵の回答を聞いた眞代はニコッと笑った。
「じゃ私達、悪者コンビだね!」
(コンビ?)
反射的に、盗賊のおじさんと意地悪お妃が肩を組む姿を想像してしまった。お妃はすぐに葵の顔になったが盗賊の顔は眞代にならない。
(盗賊って感じじゃないもん)
猫なら分かる。猫耳の付いたカチューシャをつけて、「ニャー」とか言ったりして。
(あれ、こんなふうに他人についてあれこれイメージしたことあったっけ?)
今の自分に、少し困惑してしまう。
「え、てか」
いつの間にか萌々が葵の手元を凝視している。
「アオイっちのお弁当すごくない?」
「あっ確かに」
眞代が手元をのぞき込んでくる。
「唐揚げ、餃子、野菜のオムレツ、スパゲッティ、ポテサラ、タコさん・・・じゃないウインナー、え、白ご飯じゃなくて炊き込みご飯?」
「そうだよ」
(鯛と梅の炊き込みご飯)
「豪華だねー。アオイっちのママすごいねぇ」
「あ、ううん? 作ったのパパなんだ」
葵の父は専業主夫だ。たまにパートに出ることもあるが、基本的にはずっと家にいる。家事やら葵の世話やら、何もかもやってくれるありがたい父親だ。
『ねぇ葵、パパと遊ぶのもいいんだけどさ・・・』
ブンブン、と頭を振った。思い出したくもない言葉だった。
「あーまあ言われてみたら、ザ・男って感じのラインナップだねぇ」
「量も多いし」
「てか葵ちゃん、一人でこんな食べられるんだ?」
話が父親から逸れてくれてホッとした。言われて見比べてみると、葵の弁当箱ーというかタッパーーは、他三人の楕円形の弁当箱の三倍はある。
「アオイっちって、大食い?」
(なのかな、あんまり考えたことなかったけど)
「ねえ」
翠が空の弁当箱をしまいながら言った。
「お菓子交換しよ」
「いいねぇ。モモ、棒付きキャンディ持ってきたからみんな食べてー」
「ちょっと二人、まだ葵ちゃんはお弁当食べてるんだよ?」
「ああ、私は大丈夫。お菓子交換始めてもらってて」
「そ、そう? まあでも私は待つね」
(別に良いのに。ここに混ぜてもらっただけで十分なのよ?)
まあ、葵がどう思おうが流石に待たせるのはまずい。幸い咀嚼は早い方だ。早く、だがよく噛みパパっと平らげた。
「ご馳走様でした」
「あ、終わったぁ? 二人とも、早くお菓子出してよぉ」
「もー、ちょっと待ってよ」
眞代がリュックから赤い巾着を取り出す。口を開けると、中に一口サイズの羊羹や最中が見えた。
「好きに取っていいよー」
「こっちもどうぞ」
萌々は個装のキャンディやチョコを大袋から空け、翠はポテトチップスの袋を平らに破いて皆が取れるようにした。
葵はと言うと、弁当と同じくらいのサイズのタッパーを取り出した。パカッと蓋を開ける。
姿を現した丸形のドーナツの山に、六つの目はたちまち釘付けになった。
「よ、よければ・・・」
「え、すごーい。これ手作りだよねぇ。アオイっちのパパ、デザートも作ってくれるんだぁ」
「う、ううん。これは自作だよ」
あんな豪華な弁当を作ってくれる父に、それ以上の負担は掛けられない。
「え、それマジ?」
「すごいなあ葵ちゃん、よくこんなの作ったね」
感心する萌々と眞代をよそに、翠がおもむろにドーナツに手を伸ばした。
もぐもぐもぐ、と黙って咀嚼する。
「二人もどうぞ」
促すと、眞代と萌々も一つずつ取って口に運んだ。
「!」
「!」
「美味しい」
一口目を飲み込んだ二人が感想を言うより早く、翠が一言そう述べた。そして二つ目に手を伸ばす。気に入ってくれたみたいだ。
「バナナドーナツなんて初めて食べた」
「プレーンじゃ物足りないかなって思ってバナナを入れたんだよね・・・」
「アオイっち、手間かけたんだねぇ」
「甘いもの好きだから・・・」
普段料理はあまりしないが、お菓子作りはよくする。甘いものは体だけでなく心の栄養になる。癒しをくれる。
(ぼっち飯の時なんかは特にね)
「葵、甘いもの好きなの?」
不意に翠が問いかけてきた。
「う、うん。好きだよ」
少し戸惑いつつ返答する。ここに来て、この無口な少女に話しかけられるなんて思いもしなかった。だが翠は「ふーん」と言ったきり言葉を続けない。何を言いたいのだろうか。
そこで、二人の様子を見ていた眞代が「あっ」と声を上げた。
「葵ちゃん、スイーツビュッフェって行ったことある?」
「う、ううん。ないよ」
「じゃあさ、行く気ある?」
(おや、これは誘われる流れか?)
90%そうなのだが、お誘いに縁がなさ過ぎて確信が持てないでいる。
「あ、甘いもの好きだから、いつか行ってみてもいいかなって思ってるけど・・・」
「じゃあさ、今月末行こーよ、スイーツビュッフェにさぁ」
萌々が身を乗り出してくる。どうやら本当に誘われているらしい。なんという急展開だろう。
「ビュッフェ行こうって話してたんだけどさぁ、この三人だとどう考えても全制覇無理じゃん?」
(・・・ははあ、スイーツ好きの大食いとして、お眼鏡にかなったようですな)
どうしようかな、と考える。今みたいに会話についていけず孤立する展開は全然ある。でも、スイーツをたっぷり食べていれば十分有意義な時間になるだろう。
「う、うん。いいよ」
「ありがとー葵ちゃん」
眞代が嬉しそうに手を叩く。
「じゃあ、また今月末に会おうね」
「てかさ、今日早速遊ばなーい?」
「賛成」
「そうだね。宿題もないしね。どうかな葵ちゃん?」
「へ?」
これは流石に、急展開すぎるにもほどがありすぎる。
ーー
午後二時過ぎ。社会見学を終えた葵が帰宅すると、エプロン姿の父が台所で鍋をかき混ぜているところだった。
「おっ、お帰り」
「ただいまー」
肉や野菜がケチャップソースと赤ワインで煮込まれる匂い。今夜はビーフシチューに違いない。
「遠足はどうだった?」
「ん、まあまあ。お弁当は美味しかったよ」
「そっか、良かった。あ、今日の相手をするのはちょっと待ってね。これ作り終わったら声を掛けるからさ」
「あ、そのことなんだけど」
葵は弁当箱を流しの傍に置き、棚のお菓子箱を開いた。
「今日はこの後出かけるから、夜になったらお願い」
「出かけるってどこへ?」
「隣のクラスの人の家。だからお菓子持って行くね」
「え?!」
父親は手を止め、葵の顔をまじまじと見た。驚きと、喜びの入り混じった表情をしている。
「友達ができたのかい?!」
「うーん・・・」
今日会ったばかりだし、友達というほどの仲ではないはずだ、多分。
「そういうんじゃないかな。一緒にお弁当食べたらなんかそういう流れになって」
「うーん、いやそうかそうか。何でもいいんだ。良かった良かった」
父親はうんうんと頷いている。
「で、何をして遊ぶんだい?」
「特に聞いてない」
「じゃあ、どれか一つ持って行ってみれば?」
父親は目線でリビングの壁を指す。その一角が棚になっていて、ボードゲームの箱がぎっちりと収められている。シンプルな軽量タイプから、設定もりもりのヘビーゲームまでたくさんの種類が取り揃えられていた。
葵にとっては最高の宝物。だが、他の人にとっては必ずしもそうではない。
「うーん、そういうノリじゃなさそうだからいいや」
葵はお菓子だけ紙袋に入れて棚に背を向けた。ボードゲームは父親とだけやっていればいいのだ。
(ボードゲームが好きなんて言ったらさ、オタクだって馬鹿にされるに決まってるよ)
小学生の頃、一度だけ同級生を家に呼んだことがある。「こんなのが好きなの? なんかおじさんみたいだね」と笑われて揶揄われた。だからそれ以来、ボードゲーム好きを外で公言したことはない。
今日も、これがバレるのが嫌で萌々の提案を断ったのだ。
『葵っちの家行ってもいい?』
『あーごめん、うちは散らかってて』
『そっかぁ。じゃあモモん家か、ミドリンの家だね』
そんなわけで、今から萌々の家にお邪魔するのだ。
「じゃあ行ってきます」
「はあい、気をつけてね」
支度を整え、葵は再び家を出たのだった。
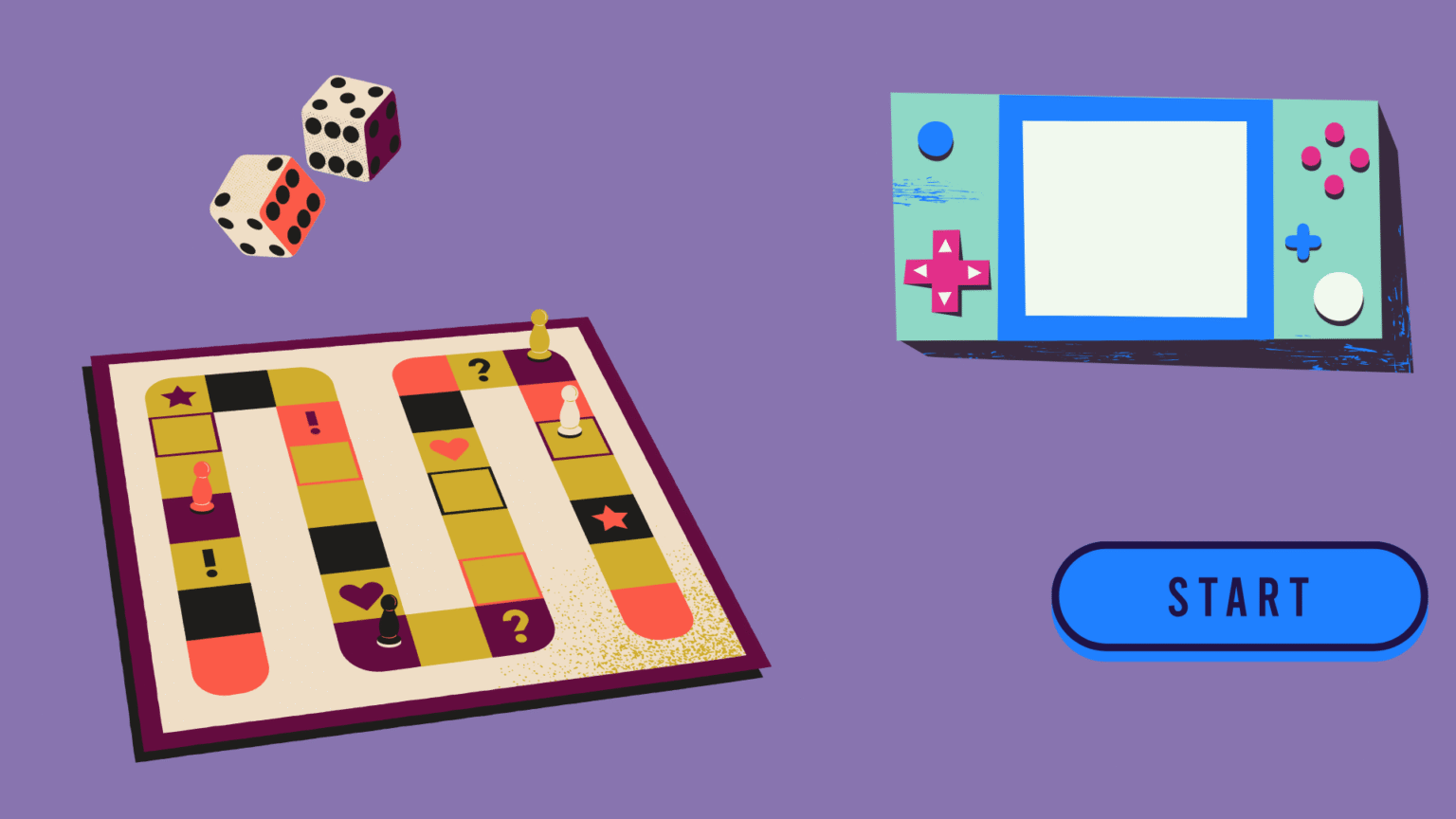
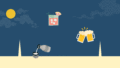
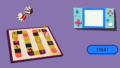
コメント